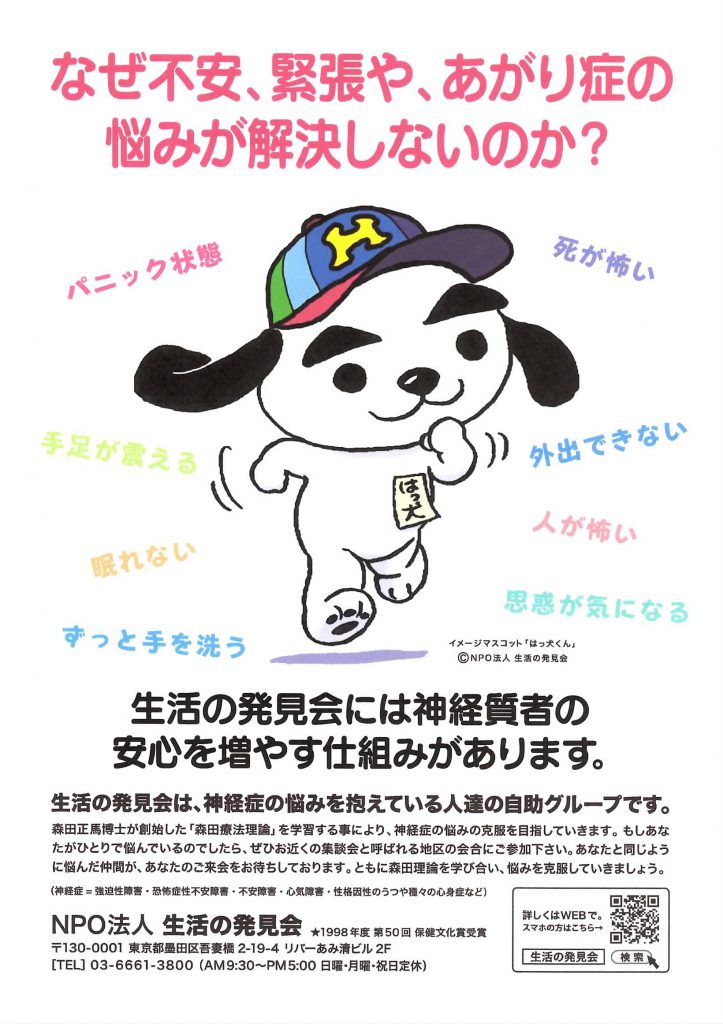全集第5巻読書会と体験交流を毎月開催中
「森田先生の人間観とは?」
「森田療法・理論の世界観とは?」
全集5巻を通して、森田先生の時代に立ち返り、日々の生活と森田療法の学びが交差するような、温かな時間になればと思っています。
大切にしたいのは、ただ「知る」ことだけではなく、自分のこころの事実にふれてみること、そして、それを言葉にしてみること。
読書の中で心に残った一節、自分の生活でふと気づいたこと、今まさに感じていること――それぞれが率直に語り、じっくりと耳を傾ける時間といたします。
●メンバーとの共通する感情に「ああ、そうなんだな」と気づくこと
●浮かんできた想いを、そのまま言葉にしてみること
● 生活の中の小さな出来事を、具体的に分かち合ってみること
● そして、何よりも「共感」と「受容」を大切に、お互いの声を受け止め合うこと
こうしたプロセスを通じて、森田療法が目指している“あるがまま”の姿勢や、“生きる力”の源に、あらためて触れたいと思います。
大事なのは集うことの豊かさです。
読むこと、語ること、聞くこと――そのどれもが、人と人とのあいだに静かな灯をともしてくれるのだと実感しています。
毎回、日々の生活と森田療法の学びが交差するような、温かな時間をつくっていければと思っています。
第7回形外会ー昭和5年11月9日(午後3時開会、参加者29名)
森田先生のお言葉
・僕は身内の者の死にあったのは、高等学校時代に伯母と大学卒業後に弟が旅順で戦死し、大正12年に父が71才で亡くなり、今度は子供を亡くした経験を持っています。
・しかし感情はそのように簡単ではない。当然に死ぬべき病気でも親の心は最後まで、これを死ぬとは思わず、奇跡的にも助かると思い、また死んでも帰ってくるような気がし、灰になっても、まだなくなったように思わない。
・死んだという事の意味を明瞭にする事が恐ろしい。これは理知でなくて、そのままの感情そのものである。こんな風であるから、その直情のままに、悲痛に迫って、小児のように慟哭する。
・純なる感情であるから、日を経るままに、しだいにその悲しみも薄くなり、忘れられるようになる。小児の感情が、早く変化しやすいのもこのためである。(p66-p67)
・山野井君は入院中、あまり書痙が治り難いから一時退院してみる事に相談しました。そのとき、同君は会社を辞職して田舎に帰ると申しますから、 私はもし田舎に帰れば、書痙は決して治らぬが、強いて会社に行っていさえすれば、必ず治るといって忠告しました。で、同君は、そのまま従順に私の言う通り実行したのであります。従順とは、自分で訳のわからぬままに、信ずる人のいう事を、試みに実行する事であります。自分に理由が納得され、なるほどそれに相違ないと分かって,後にする事は従順とは申さないのであります。(p77)
「悲しみと従順と」──森田先生のお話しから学ぶこと(分かりやすく)
森田先生は、若いころから多くの身近な人の死に立ち会いました。
高校時代には伯母を亡くし、大学を出たあとには弟が戦争で命を落としました。さらに、大正12年には父親が71歳で亡くなり、その後には子どもまでも見送ることになります。
けれども先生はこう言っています。
「感情というものは、そう簡単には割り切れないものだ」と。
たとえ、病気が重く、もう助からないと頭ではわかっていても、親の心は最後まで「きっと助かる」「もしかしたら奇跡が起こる」と信じてしまう。
亡くなったあとでさえ、「そのうち帰ってくるような気がする」「灰になっても、まだどこかにいるように思える」。
それが人の心の自然な姿だ、と先生は語ります。
そして、「死んだという事実をはっきりと認めるのは、恐ろしいことだ」とも言いました。
これは理屈ではなく、心そのものの反応です。
だからこそ、悲しみがあふれ出して、子どものように声をあげて泣くのです。
けれども、そんな純粋な感情は、やがて時間とともに静まっていきます。
悲しみは少しずつ薄れ、やがて日常の中に溶けていく。
子どもの心が変わりやすいのも、感情がまっすぐで純粋だからだと先生は言います。
あるとき、森田先生のもとに「書痙(字を書こうとすると手が震える症状)」で苦しむ若い人が入院していました。
名前は山野井君。症状がなかなか良くならないので、「一度田舎に帰ろうと思います」と相談しました。
先生はすぐにこう答えました。
「田舎に帰れば、決して治らない。けれども、会社に行き続ければ、きっと治る」と。
そして山野井君は、先生の言葉を信じて、そのまま実行したのです。
森田先生は、このときのことを「従順」と呼びました。
それは、自分ではまだ納得できないけれど、信じる人の言葉を試しにやってみること。
「なるほど、そういう理屈か」と理解してから行動するのは、従順ではないのです。
信じるというのは、理屈ではなく「試してみよう」という素直な心の動きから始まります。
そして、その一歩が、回復の道をひらく。
悲しみを受け入れることも、信じて行動することも、どちらもすぐにはできません。
でも、森田先生が教えてくれるのは、「心は時間とともに自然に動いていく」ということです。
感情を抑えつけるのでもなく、理屈で片づけるのでもなく、ただそのままの自分の心を見つめながら、生きていく。
それが、森田療法の原点なのかもしれません。
「そのままの悲しみと、やってみる勇気」
──森田先生のお話から(高校生〜大学生の若者を想定したストーリーテイスト)
「ねぇ先生、人の死って、どうやって受け入れたらいいんですか?」
大学の心理学ゼミのあと、僕はぽつりと聞いた。
親しい人を亡くしたばかりで、頭の中はぐるぐるしていた。
もういないってわかっているのに、まだどこかで「帰ってくるんじゃないか」と思ってしまう。
森田先生は、少しだけ間をおいて話し始めた。
「僕もね、たくさんの人を見送ってきたんだ。伯母、弟、父、そして子どももね。」
その声には、静かな深みがあった。
「でもね、人の心ってそんなに簡単に整理できるもんじゃない。
頭では“もう死んだ”とわかっていても、心は“いや、きっと助かる”“また会える”と思ってしまうんだ。
死んだという現実を、はっきり認めるのが恐ろしい。
それが自然な感情なんだよ。」
僕は黙ってうなずいた。
先生はさらに続けた。
「だから、悲しくて泣くことも、悪いことじゃない。
むしろ、それでいいんだ。
悲しみは純粋な感情だから、抑えようとせずにそのまま流れるままにしておく。
そうすると、時間とともに少しずつやわらいでいく。
無理に“立ち直ろう”なんてしなくてもいいんだよ。」
先生の言葉を聞きながら、僕の中で少しずつ何かが動いた。
“悲しんでいい”という言葉が、不思議と優しく響いた。
数日後、僕はもう一度先生の部屋を訪ねた。
「先生、書くことが苦しくて……。
レポートを書こうとすると手が震えるんです。焦っても進まないし、もうやめた方がいいんじゃないかって。」
先生は少し笑って言った。
「それはね、昔、同じように悩んでいた学生がいたよ。山野井君っていうんだ。
彼も“字が書けない”って言ってた。で、あまり治らないから、田舎に帰ろうとしたんだ。」
「帰ったんですか?」
「いや、僕が止めた。
“田舎に帰ったら治らない。会社に行き続ければ、必ず治る”ってね。
彼は信じて、そのままやってみたんだ。
理由はわからなくても、“信じてやってみる”――これを僕は“従順”と呼んでいる。」
「従順……?」
「そう。納得してからやるんじゃなくて、納得できなくても“やってみる”。
頭で考えすぎず、行動してみる。
森田療法の基本は、“あるがまま”を受け入れて、“やるべきことをやる”ことなんだ。」
先生はそう言って、僕の目を見た。
「心の震えも、手の震えも、自然な反応なんだよ。
大事なのは、それを消そうとしないこと。
震えながらでも、書いてみる。悲しみながらでも、生きてみる。
それが、本当の“生きる力”なんだ。」
その日、僕は机に向かった。
相変わらず手は少し震えていた。
でも、ページに文字が少しずつ並んでいくのを見て、なぜか少し安心した。
「悲しみも、震えも、いまの自分なんだ」
そう思えたとき、ほんの少し、心が静かになった。
正一郎の一周忌が近づいた。死んだといふ悲しみが緩解されると共に、別れて後の彼は、次第に遠い遠い国へ、先へ先へといってしまったやうな心持がする事がある。自分も死ねば、急いで追付いて会う事が出来るやうにも思われる。之を黄泉の国とでも云ふであらうか。
『森田正馬全集第7巻・亡児の思い出』(代表幹事追記)