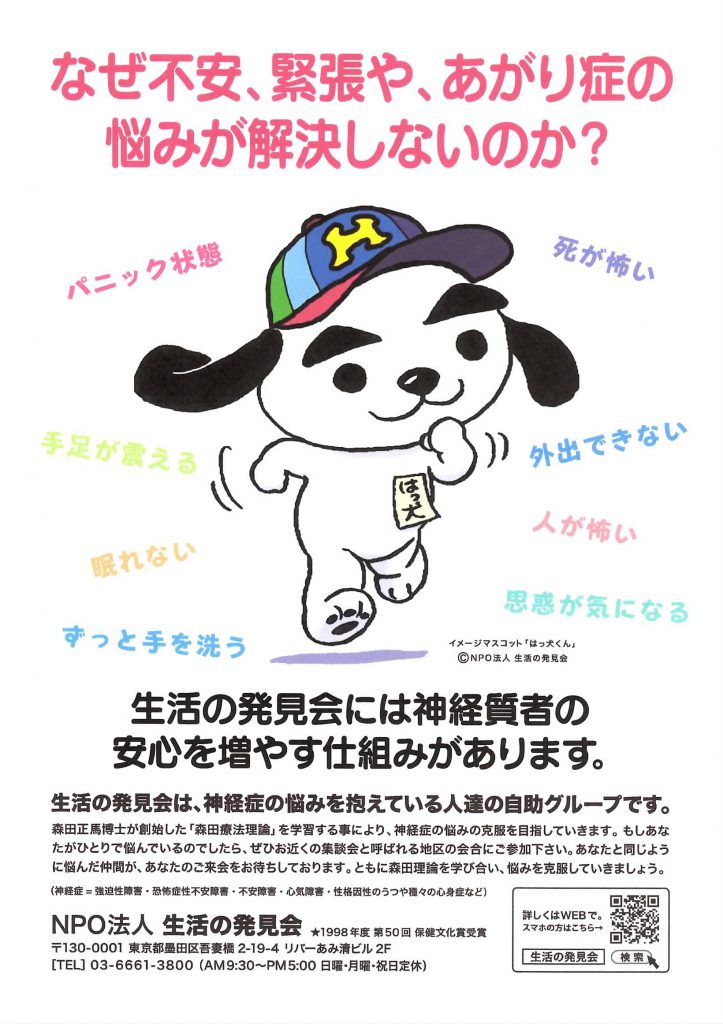10月度の下丸子土曜集談会は無事に終了しました。
女性懇談会には7名、定例会には11名の参加があり、いずれも和やかな雰囲気の中で活発な体験交流が行われました。
自助グループでのボランティア活動は、自らの心と向き合いながら、参加者同士の受容と共感を体験する貴重な場となっています。こうした実践は、社会人としての「心の準備」を育む意味でも大きな意義があります。
近年、就職活動においては、単なる学業成績や資格の有無だけでなく、「社会的活動への参加」が重要な評価項目として注目されています。ボランティアや地域活動、自助グループなどに関わる経験は、主体的に人と関わり、協働し、社会に貢献しようとする姿勢の表れとして高く評価されています。
大学生の時期に、森田療法や生活の発見会の活動を通じて多様な世代と出会い、語り合い、共に考える経験は、自らを見つめ直す貴重な機会となります。人との関係の中で、思い通りにならない現実を受け入れながら、それでも前に進む力を学ぶことは、社会に出た後の人間関係や仕事の場面で必ず生きてきます。
「他者とともに生きる力」や「自他理解の深まり」は、机上の学問だけでは身につかない、実践の中でこそ培われるものです。こうした経験を通じて培われる柔軟さと共感力こそ、現代社会を生き抜く上での大切な資質といえるでしょう。
(代表幹事の独り言)
最近の就職活動では、ただ勉強ができるとか、資格を持っているというだけでは通用しないらしい。
企業はその人がどんなふうに他人と関わり、社会とつながってきたかを見ている。
つまり、どんな人間として生きてきたか、ということだ。
そう考えると、森田療法や生活の発見会のような場所に足を運ぶ大学生がいるのは、ちょっとした希望のようにも思える。
そこでは、誰かが悩みを語り、誰かがただ黙って耳を傾ける。
気の利いたアドバイスなんていらない。
大切なのは、ただ「そこにいる」ということだ。
僕もそんな空間に何度か身を置いたことがある。
言葉にならない気持ちが少しずつ形を持ちはじめ、
他人の話を聴いているうちに、自分の中にも似たような痛みがあることに気づく。
人と人との境界が、ほんの少しだけ透けて見える瞬間がある。
大学生のうちにそういう時間を持てるというのは、実に貴重なことだと思う。
社会に出る前に、「自分とは何か」「人と生きるとはどういうことか」を肌で感じておく。
それは将来、仕事に追われる日々の中でも、心のバランスを取り戻す小さな支えになるはずだ。
社会活動というのは、結局のところ「生き方のリハーサル」みたいなものかもしれない。
完璧じゃなくていい。
うまくいかないことの中にこそ、人とつながる余白が生まれる。
そしてその余白こそが、生きることの温度を保ってくれる――そんな気がしている。