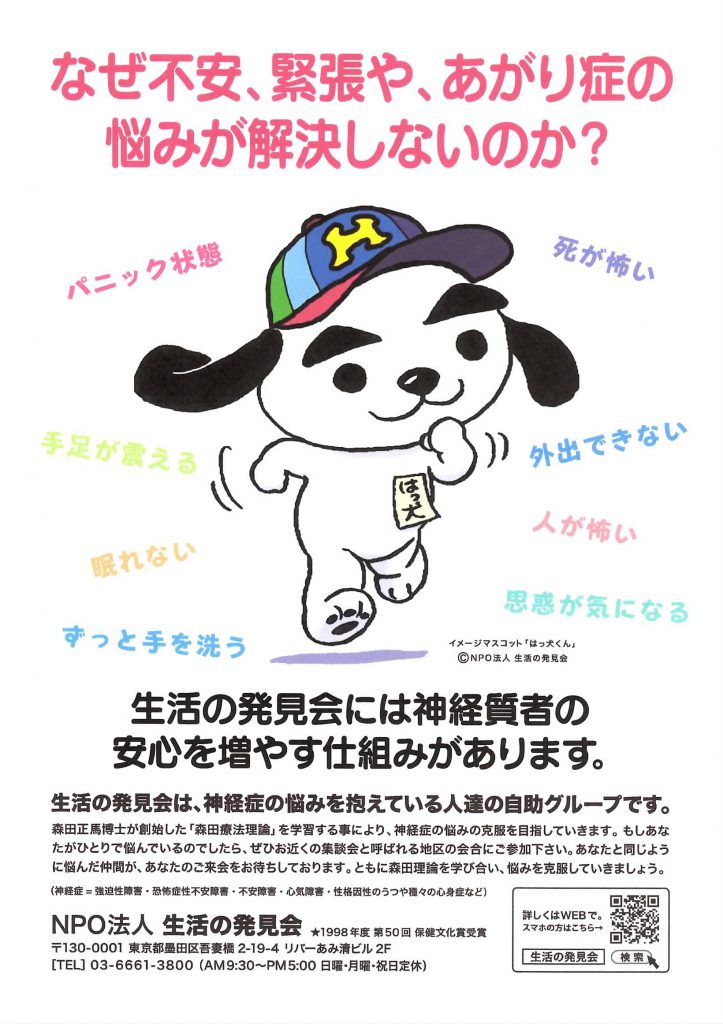下丸子土曜集談会は、今月も無事に終えることができました。女性懇談会には4名の方が、例会には11名の方が参加してくださいました。
それぞれの自己紹介や体験交流の中で語られた言葉を、ひとつひとつ大切に受けとめながら、森田療法とのつながりや、そこにひそむ接点を少し探ってみたいと思います
■ひきこもりの子どもを持つ親の立場からの発言についてのノート
ひきこもりの子どもを持つ親の悩みとは
- 将来への不安
子どもがこのまま社会に出られないのではないか、経済的にも自立できないのではと心配する。 - 親としての自責感
「自分の育て方が悪かったのではないか」「もっと早く対応していれば」と、過去を悔やむ気持ちが強まる。 - 孤立感と世間体
周囲に理解されず、親自身が人に相談しづらく孤立してしまう。「世間に知られたくない」という思いからさらに閉じこもる。 - 対応の難しさ
子どもに無理やり外に出させるべきか、そっとしておくべきか、声をかけるタイミングや言葉選びに迷う。
森田療法のとらえ方のヒント
- 「あるがまま」の姿を受け止める
ひきこもりは一時的な「症状」としてとらえ、すぐに消そうとするよりも、まずはその現実を認める姿勢を持つ。 - 不安や焦りも自然な感情
親の心配や不安も「感じてはいけない」ものではなく、自然な心の働きと理解する。無理に打ち消す必要はない。 - 行動を通じた変化を重視
森田療法では思いを操作するより、現実の生活の中で小さな行動を積み重ねることを重視する。
親も「子どもの変化を待つ」だけでなく、自身の生活や役割を大切にして行動を続ける。 - 症状は人生の一部
ひきこもりの状態そのものが、その子の生き方の中で意味を持ち得る。長期的に「症状と共に生きる」視点も必要になる。 - 親自身の生活重視
子どもをどうにかしようとするあまり、親自身が生活や人生を犠牲にすると共倒れになりやすい。
まずは自分の生活を整え、安心した土台から子どもに関わることが望ましい。
方向性として
「ひきこもりをすぐに治そうと焦るより、親も子もそれぞれの生活を大切にしながら、現実に即して少しずつ関わりを続ける」
というのが、森田療法的な立ち位置だとまとめられます。
■親、特に母親でトラウマ状態の女性のお話しについて
「母親との関係でトラウマを抱えた女性の悩み」と「森田療法との接点」を、整理してみました。
- 母親との関係で生じる悩み(典型例)
- 自己否定感
小さい頃から「ダメな子」「親の言う通りにすべき」といった強い支配や否定を受け、自分に自信を持てない。 - 罪悪感と恐れ
母親に逆らうことや距離をとることに罪悪感を感じ、自由に生きたいのに心の中では強いブレーキがかかる。 - 対人関係の困難
他人との関係にも「支配されるのでは」「拒絶されるのでは」という不安を持ちやすく、親密な関係づくりが難しい。 - 過去にとらわれる苦しさ
母親から受けた言葉や態度を思い出し、現在も感情的に支配され続けるように感じる。
- 森田療法との接点
森田療法は「症状や感情を取り除く」ことを目指すのではなく、
「感じながら、その中で生きていく力を育てる」立場に立ちます。
- 過去の体験や感情は消せないが、生き方は選べる
母との関係によるトラウマ記憶や感情は、無理に消そうとするほど強まることがある。森田療法では「消そうとしない」ことを基本に据え、感情を抱えながら現実の生活を営む方向を大事にする。 - 不安や怒りを「自然な感情」として扱う
「母を憎んではいけない」「いつまでも苦しむのは弱い」と否定するのではなく、そう感じるのは人として自然な反応だと理解する。 - 「症状本位」から「目的本位」へ
母親との葛藤や過去の苦しみにとらわれて生きるのではなく、自分がこれからどう生きたいか、現実にどんな行動をとれるかを中心に据える。 - 小さな現実行動からの回復
過去を掘り返すのではなく、今日の生活(掃除・仕事・趣味・人との交流)を積み重ねることから、「生きる力」が再び育っていく。 - 自分の生活を「拠点」にする
母の声が頭に残り続けても、自分の生活・役割・楽しみを大事にすることで「過去に支配されない時間」を広げていける。
まとめ
「毒親の記憶を消す」ことは難しいけれど、森田療法的には “感情を抱えたまま、現実の生活を営むこと” が回復への道になります。
■インナーチャイルドのお話しについて
インナーチャイルド(内なる子ども)を癒すアプローチと、森田療法の立場を並べると、それぞれ方向性が違いながらも「接点」が見えてきます。
- インナーチャイルド療法の基本的な立場
- 幼少期に傷ついた「内なる子ども(感情・欲求)」を見つめ、対話し、癒すことで心の回復をはかる。
- 「過去に十分に満たされなかった思い」を扱い、心の奥にあるニーズを認めることを重視する。
- 主眼は「感情のケア」と「自己受容」。
- 森田療法の基本的な立場
- 感情や症状を変えようとするのではなく、「あるがまま」に受け入れ、現実の生活行動を通じて生きる力を育てる。
- 「不安や葛藤は自然な感情」ととらえ、無理に取り除かず、生きる目的や役割に従って行動を優先する。
- 主眼は「行動による生活の充実」と「自然良能(人が本来もつ回復力)への信頼」。
- 両者の接点
- 自己受容
インナーチャイルドは「過去の傷ついた自分を否定せず受け止める」ことを重視する。
森田療法も「不安や葛藤を排除せず、そのまま認める」ことを基盤にする。 - 感情は変えようとしない
インナーチャイルドは「満たされなかった気持ちを受け止める」。
森田療法は「消そうとせず、そのまま抱えたまま生きる」。
両者とも「感情操作よりも受容」を共通点としている。 - 回復の方向性は“今ここ”から
インナーチャイルドは「過去の子ども時代を癒す」が、最終的には「今の自分が生きやすくなる」ことが目的。
森田療法は「過去を掘り下げない」が、「現在の生活行動の充実」を通じて結果的に感情も安定していく。
→ 両者とも「現在の自分を生きる」方向に収束する。 - 人間の自然な欲求に注目
インナーチャイルドは「愛されたい・承認されたい」という人間の基本的欲求に光をあてる。
森田療法も「生の欲望(生きたい・成長したい)」を人間の根源ととらえ、これを信頼する。
- 相違点もふまえた使い分け
- インナーチャイルドは「過去に癒しを求める」方向に目を向けやすい。
- 森田療法は「過去はそのままに、今を生きる」方向に焦点を合わせる。
- 接点は「感情を否定せず、今ここで生きる力を取り戻す」というところにある。
まとめ
インナーチャイルド療法は「過去の自分を抱きしめて癒す」ことで、
森田療法は「不安や痛みを抱えながら現実を生きる」ことで、
どちらも最終的に「自己受容と生活の充実」を目指しています。
■AA12ステップのお話がありました。
AAの12ステップと森田療法を並べて考えると、出発点は違いますが、不思議と接点が多く見えてきます。
- AAの12ステップの基本
アルコホーリクス・アノニマス(AA)は、アルコール依存からの回復を支援する自助グループです。その核心にあるのが「12ステップ」という行動指針です。
要点を整理すると、以下の流れになります:
- 自分の無力さを認める(アルコールに対してコントロールできない)
- より大きな力(ハイヤーパワー)への委ね
- 自分をゆだねる決断
- 内省(自分の棚卸し)
- 自分の過ちを神・自分・他者に告白
- 人格の欠点を手放す準備
- 欠点を取り除いてもらうよう祈る
- 傷つけた人のリストを作る
- 償いをする
- 日々の棚卸しと修正
- 祈りと瞑想によってハイヤーパワーとの関係を深める
- 他者への奉仕(メッセージを伝え、実践する)
要するに、
- 無力さの自覚
- 受容と委ね
- 内省と告白
- 償いと修正
- 日々の実践と奉仕
というサイクルです。
- 森田療法との関係
森田療法は依存症治療のために作られたわけではありませんが、「あるがまま」「症状を変えようとせずに生きる」という姿勢が、AAの12ステップの精神と通じます。
- 無力さの受け入れ
AAは「アルコールに対する無力さ」を認めます。森田療法は「不安や恐怖は自然に起こるものであり、なくそうとあがいても無駄」と説きます。両者とも「コントロール不能なものを認める」ところから始まります。 - 委ねる姿勢
AAは「ハイヤーパワーに委ねる」。森田療法は「自然良能にまかせる」。言葉は違いますが、自分の力で完全に支配しようとせず、流れに従うという姿勢は共通しています。 - 内省と受容
AAでは棚卸し(内省)を行い、自分の過ちを告白します。森田療法では「あるがままの自分を受け入れる」。どちらも「理想の自分像とのギャップを責めずに、現実を直視する」ことを求めます。 - 行動による回復
AAでは「償い」「奉仕」という実践が重要。森田療法でも「症状にかかわらず、日常生活・仕事に取り組む」ことで回復していきます。つまり、頭の中ではなく行動の中で変わるという点が同じです。 - 日々の継続
AAは「毎日の棚卸し」「祈り・瞑想」を重視。森田療法は「日々の生活を営むこと」そのものが療法。どちらも一度で終わるものではなく、生活全体の習慣として続けることを強調します。
- 違い
- AAは「ハイヤーパワー」という超越的な存在への信頼を前提にしている。
- 森田療法は「自然(本来備わった回復力)」への信頼であり、宗教的ではない。
まとめ
AAの12ステップと森田療法は、表現は違いますが、
- 無力さを認める
- 自然や大いなるものに委ねる
- あるがままの自分を受け入れる
- 行動を通じて回復する
- 日常の中で継続する
という核心で響き合っています。
■生活の発見会の基準型学習会参加について多数の体験談が上がりました。
「90日間の集中した森田療法理論の学習」が受容と共感の面でどのような効果をもたらすかを整理してみると、
- 学習の枠組み
森田療法は単なる「知識」ではなく、生き方に直結する心理療法の哲学です。90日(約3か月)というまとまった期間、体系的に学ぶことで、知識の理解にとどまらず、実感を伴った受容と共感の力が養われます。
- 受容面での効果
- 自分の症状・感情の受け入れ
- 森田理論を繰り返し学ぶことで「不安・恐怖・緊張は自然の働きであり、なくそうとしなくてよい」と理解が深まります。
- 90日間の学習を通じて、知識が「頭の理解」から「心の納得」へと変化し、症状を抱えながらでも生活していけるという受容の姿勢が強まります。
- あるがままの自分を肯定できる
- 短期的な講座では「知ったつもり」で終わりがちですが、3か月継続すると、日常の出来事に森田の視点を重ね合わせて体感できます。
- 「理想の自分」ではなく「今の自分」を肯定する力が徐々に身についてきます。
- 共感面での効果
- 他者の苦悩を理解する視点が養われる
- 森田療法では、人間誰しも「不安」「とらわれ」を抱えていることを前提にします。学習を続けることで、他者の苦しみを「自分と同じ人間の営み」として理解しやすくなります。
- これは、単なる理論学習ではなく、自分の症状体験と重ねながら学ぶ過程で自然に培われます。
- 傾聴力の向上
- 90日間の反復学習で、森田の「説明せず、矯正せず、あるがままを聴く」という姿勢が身に付きます。
- これは対人関係において「相手を直そうとせず、共にいる」態度へとつながります。
- 共同体感覚の深化
- 森田の集談会や自助的学びでは、「同じように悩んでいる仲間」がいることを知ること自体が共感体験になります。
- 90日の学習期間で仲間との共有が積み重なれば、孤立感が和らぎ、人間関係の安心感が広がる効果があります。
- まとめ
90日間の集中学習は、
- 受容:自分の症状や感情を「あるがまま」に受け入れる姿勢が深まる
- 共感:他者を直そうとせず、苦しみを共に味わう姿勢が育つ
という二つの効果を強めます。
短期的な理解が「知識」で終わるのに対し、90日という期間は生活実践と結びつき、心の態度そのものを変える学びとなる点が大きいのです。
今月も下丸子土曜集談会を無事に終えることができました。自己紹介や体験交流を通して心に残る言葉が交わされました。
その一つひとつを振り返り、森田療法とのつながりや接点を見つめ直すことで、来月の語り合いにもつながる手がかりが見えてきたように思います。
来月もまた、ゆったりとした時間の中で、たっぷりと語り合いましょう。
今月のご参加、本当にありがとうございました。(代表幹事)