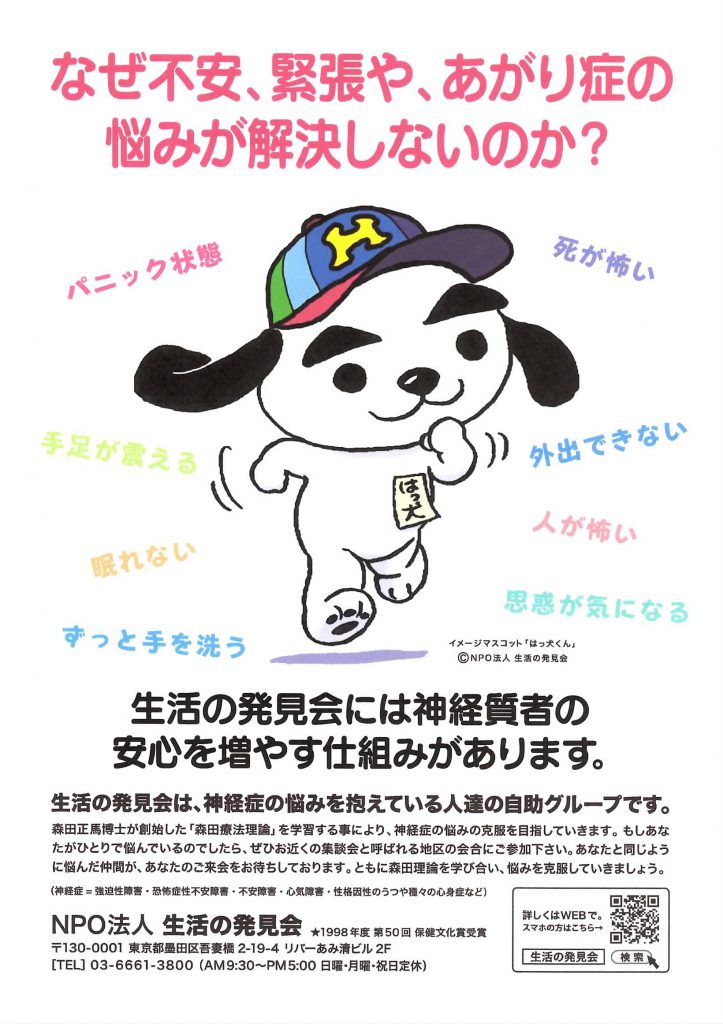26日の下丸子土曜集談会報告-池上会館小研修室から
昨日の集談会には、参加者13名(男性9名、女性4名)と、派遣講師の出席がありました。連日の猛暑にもかかわらず、多くの方が足を運んでくださり、実りある時間となりました。
今回の講話では、講師ご自身の体験をもとに、症状との向き合い方や回復の過程が語られました。そのなかから、印象に残った言葉をいくつかご紹介いたします。
まず、「落ち込みの回復には、生の欲望の活動があった」との言葉がありました。何かをしたい、こう生きたいという内側からの自然な欲求が、回復への力となるという話に、多くの参加者が頷いておられました。
また、生活の発見会に入会後、一度は回復を感じたものの再発してしまった経験についても触れられ、「原因は“治りすぎ”による様々な勘違いだった」と率直に語られました。この言葉には、治ったと思いこむことで無理を重ねてしまう危うさと、継続して自分を見つめることの大切さが込められていました。
「逃げずに自分と向き合う姿勢で症状がとれる」「この自分で生きていくよりほかにない」といった言葉には、自己受容と覚悟のようなものが感じられ、心に残りました。
さらに、「人間の持つ自然治癒力を引き出すこと」「不安のまま、目の前のできることに手を出す」という実践的な姿勢も語られました。状況がどうであれ、自分にできる小さな行動から始めていく、その積み重ねが回復への道であるという点は、多くの参加者にとって励みとなったようです。
最後に、「態度価値に着目し、思考や行動の指針にする」というお話も印象的でした。症状や環境に振り回されるのではなく、自分がどうありたいか、どのように生きるかという価値観を基準に日々を歩むことの大切さが強調されました。
以上のように、今回の集談会は、講師の体験を通して深い気づきと実践へのヒントを得る場となりました。参加された皆さまにとっても、それぞれの今後の生活に活かせる学びが多かったことと思います。
次回の集談会は8月23日(第4土曜日)を予定しております。詳細は改めてご案内いたします。
暑さのなか、ご参加いただきました皆さまに心より感謝申し上げます。
森田療法における治り過ぎについて
「治り過ぎ」とは何か。自分を「健康でなければならない」と思い込む。症状が一時的に消失したことで、「もう自分は完全に治った」と信じ込んでしまい、再び不安や症状が現れることを強く恐れるようになります。その結果、小さな揺らぎや不調にも過敏になり、「こんなはずじゃない」と再び症状を悪化させてしまうことがあります。
自分の「治り方」に対して理想像を持つ。「本当に治るというのは、もう何も悩まないことだ」といった非現実的な期待を持つと、そうならない現実とのギャップに失望し、「まだダメなんだ」と再び不安を強めてしまうケースがあります。
「もう治ったから大丈夫」と過信して無理をする。回復を焦って、生活リズムを急激に元に戻したり、過剰な行動をとったりすると、心身に負担がかかり再発の要因となります。森田療法は「段階的な生活の積み重ね」を重視しており、焦って「通常通り」を取り戻そうとすると、結果的に破綻することがあります。
森田療法では、「治る」とは、単に症状がなくなることではなく、症状があってもそれにとらわれずに生きる態度を身につけることを意味します。したがって、「治り過ぎ」とは、症状をなくすことを目的にした治り方、すなわち「コントロール志向」や「完全志向」に陥ることと密接に関係しています。
「治り過ぎ」からの学びとは、「治り過ぎ」を経験することも森田療法のプロセスでは貴重な学びです。回復の過程においては、何度もぶり返しながら、自分の不完全さや不安と共存していく姿勢が育っていきます。そのため、「治り過ぎ」は単なる失敗ではなく、「真の回復」に向かうための通過点ととらえることもできます。
態度価値に着目し、思考や行動の指針にすること
「態度価値(attitude value)」はもともとヴィクトール・フランクルの実存分析における価値観の一つであり、「与えられた状況にどう向き合うか」という人間の態度の取り方に焦点をあてた考え方です。これを森田療法に取り入れることで、より深い実践的意味を見出すことができます。森田療法と態度価値の接点として、森田療法は、「症状を排除せず、生の欲望に従って行動する」ことを基本とすること、そこに「態度価値」の視点を加えることで、「不安のまま、どう生きるか」、「症状を持つ自分に、どう誠実であるか」という実存的な問いが、個人の内面に深く根付き、回復を越えて自己成長へとつながる実践となります。