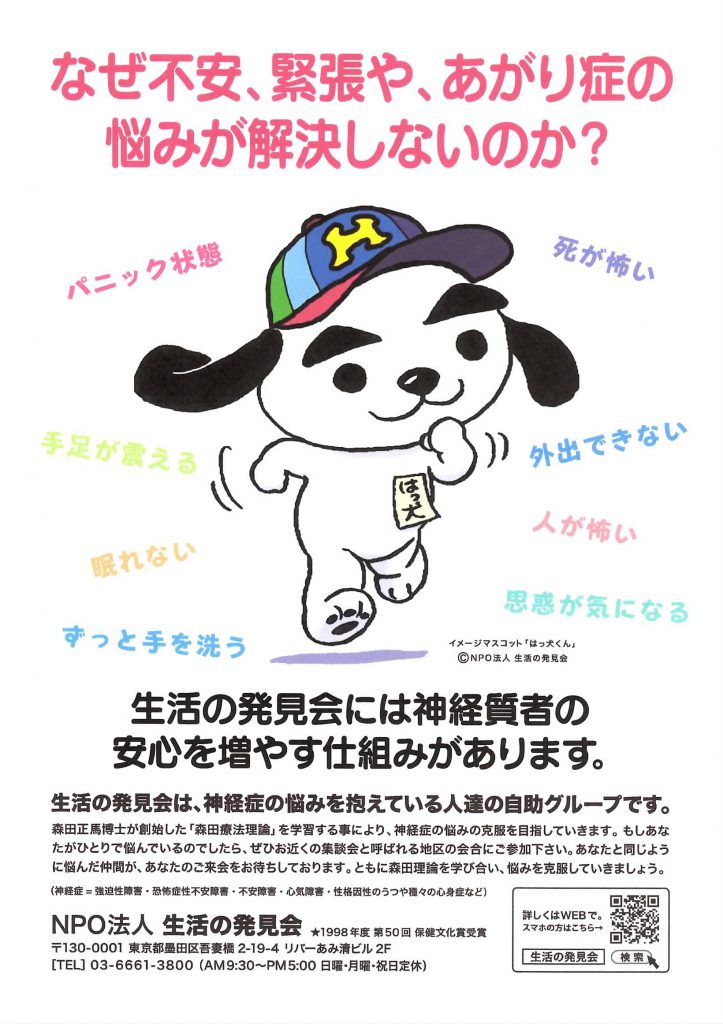全集第5巻読書会と体験交流を毎月開催中
「森田先生の人間観とは?」
「森田療法・理論の世界観とは?」
全集5巻を通して、森田先生の時代に立ち返り、日々の生活と森田療法の学びが交差するような、温かな時間になればと思っています。
大切にしたいのは、ただ「知る」ことだけではなく、自分のこころの事実にふれてみること、そして、それを言葉にしてみること。
読書の中で心に残った一節、自分の生活でふと気づいたこと、今まさに感じていること――それぞれが率直に語り、じっくりと耳を傾ける時間といたします。
●メンバーとの共通する感情に「ああ、そうなんだな」と気づくこと
●浮かんできた想いを、そのまま言葉にしてみること
● 生活の中の小さな出来事を、具体的に分かち合ってみること
● そして、何よりも「共感」と「受容」を大切に、お互いの声を受け止め合うこと
こうしたプロセスを通じて、森田療法が目指している“あるがまま”の姿勢や、“生きる力”の源に、あらためて触れたいと思います。
大事なのは集うことの豊かさです。
読むこと、語ること、聞くこと――そのどれもが、人と人とのあいだに静かな灯をともしてくれるのだと実感しています。
毎回、日々の生活と森田療法の学びが交差するような、温かな時間をつくっていければと思っています。
第5回形外会ー昭和5年5月4日(午後3時開会、参加者31名)
森田先生のお言葉
森田療法は事実唯真であるから、疑うべきは疑い、知らざるを知らずという。
腹立たしい時は腹を立て、これが心の事実であるから少しも差し支えない。
神経質の全快には心機一転することが多い、
症状は、抽象的ではなく、努めて具体的に説明することだ。
それを聴く人が、なるほどと身につまされて思い当たるところがあり、
平等間の上に立って、互いに妥協し、融通し和合することができる。
善悪ということについては、日常の心の事実を深く詳しく観察するにとどめておきさえすればいい。
体験がないうちにこうした方がよいといえば、思想の矛盾になっていけないのである。
森田療法の特徴や姿勢を分かりやすく具体的に
森田療法の根底には、「事実唯真(じじつゆいしん)」という考え方があります。つまり、頭の中で理屈をこね回すよりも、まず目の前の事実をありのままに見ることが大切だという姿勢です。
たとえば、不安を感じるときや、腹が立つとき、その感情を無理に抑えたり否定する必要はありません。「腹が立っている」というその感情こそが、自分の“心の事実”だからです。その事実をそのまま認めることが、治療や回復の第一歩になります。
神経症から回復する人の中には、ある時を境に「心機一転」するような変化を経験することがあります。しかし、それも突然変わるのではなく、日々の生活の中で自分の感情や行動を受け入れながら、少しずつ整っていくものです。
症状について語るときには、なるべく抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードや体験を交えて話すことがすすめられます。そうすることで、聞く人も「なるほど、自分にも思い当たることがある」と共感しやすくなり、対等な立場で、互いに譲り合い、理解し合うきっかけになります。
また、善悪を論じる前に、まずは自分の心の動きを丁寧に観察することが大切です。判断を急がず、体験に根ざして考えることで、真に納得のいく理解が生まれてくるのです。体験もせずに「こうすべきだ」と決めつけると、言葉と実感が食い違い、思想そのものが矛盾をはらんでしまいます。
森田療法は、頭で理解するだけではなく、実際に生活の中で感じ、体験することで深まっていく「実践の心理学」と言えるでしょう。
腹が立つときは、腹を立てていいんですよ
ある日、道ばたの植え込みに小さな看板を見つけた。
「この植物には触れないでください。とても繊細です」
ふと立ち止まり、その言葉を自分の心に向けて言ってみたくなった。
人間の心も、案外繊細なものだ。
腹が立つとき、無理に笑顔を作ってみたり、平静を装っても、どうにもこうにも納まりがつかないことがある。そんなとき、森田療法の「心の事実をそのまま認める」という考え方が、ひとつの救いになる。
「腹が立っている自分」をそのまま認める。それでいい。
感情に良し悪しをつけず、ただ「今ここにそういう気持ちがある」と見るだけで、何かがゆっくりほどけていくような気がする。
森田療法の創始者・森田正馬は、「事実唯真(じじつゆいしん)」ということばを残している。これは、「事実こそが真実である」という意味だ。人の心も同じで、理屈でどうこう言うよりも、今この瞬間の感じ方や反応こそが真実なのだと説いている。
ある知人がこんな話をしてくれた。
長年、電車に乗ることに強い不安を感じていた彼女は、あるときから「怖いけど、乗ってみよう」と思うようになった。最初は不安で手が震え、汗もにじんだけれど、それでも降りずに駅をひとつ、またひとつと過ぎた。
「そしたらね、いつの間にか目的地についていたんですよ。怖かったけど、乗り切った実感があって」
症状を治そうとするのではなく、そのまま抱えて日常を過ごす。怖さや不安は、追い払う対象ではなく、「一緒にいる」相手なのだ。
そしてもうひとつ、森田療法が大事にするのが、「具体的に語る」ということ。たとえば、「人前で緊張します」と一口に言っても、それでは曖昧だ。実際には、手のひらに汗をかき、視線が定まらず、言葉がどもる。そんな体験を、細やかに語ることで、聞き手も共感し、「自分だけじゃなかった」と思えるのだ。
語り合うときは、上から目線のアドバイスや正論ではなく、「ああ、私にもそういうところがあるなあ」と、平等の立場で、互いに身を寄せ合うような関係がいい。そこには、理屈を超えた理解や、自然な融通が生まれてくる。
「こうした方がいい」と頭でわかっていても、実際にやってみなければわからない。体験のない正論は、ときに人を追い詰めてしまう。
だからこそ、森田療法は言う。「知らざるを知らず」と。わからないことを、わからないままにしておく勇気。今ここにある自分の姿を、ごまかさずに見つめること。
それは、ちょっと不器用で、けれど確かな「生き方」なのかもしれない。