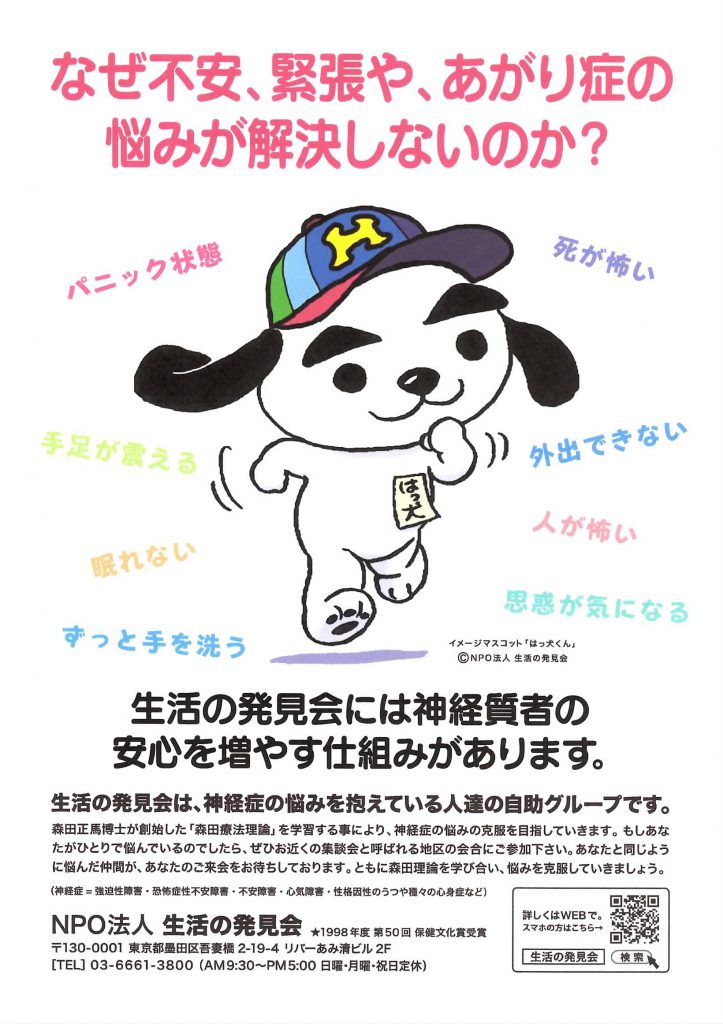機関誌『生活の発見』5月号から、新しい連載が始まりました。タイトルは「今、ここを生きる―エンド・オブ・ライフに想う―見送ること、 生きること」。人生の最終段階を見つめながら、森田療法の視点を生かした実践や、緩和ケア病棟での傾聴ボランティアの体験が語られています。
高齢の会員が多い今、このテーマはとても身近なものです。人生の終わりをどう迎えるか、その思いや準備は人それぞれですが、森田療法に根ざした生き方は、その一人ひとりに寄り添い、大きな支えになるはずです。
この連載は、「自分の生き方を、自分のこととして見つめ直す」きっかけとなる企画です。今後の展開が楽しみです。
今回は、認知症と森田療法の関係にも注目し、介護や高齢社会の中でどのように活かせるかを、実践と客観性の両面から考察しました。あわせて、日本とは異なるスウェーデンの高齢者ケアの事例も紹介します。
宮本礼子・長谷川佑子「日本とこんなに違うスウェーデンの高齢者医療・介護」
2024年4月19日 医療・健康・介護のコラム 読売新聞
「介護離職」がないスウェーデン、年間10万人を超える日本 何が違う?
日本の介護離職の背景に道徳と法的義務
日本には、家族を介護するために自分の仕事を辞める「介護離職」をする人が1年間に10万6000人(2022年)います。男女ともに55~59歳の割合が高く、介護する人にとっても、社会にとっても大きな損失です。
なぜ介護離職が生まれるのでしょうか。その理由の一つに、日本には「親の老後の面倒は子どもが見て当たり前」という社会通念があります。これは親孝行を美徳とする儒教から来ています。そのため、本人が介護施設に入りたくないと言えば、家族が家で本人を介護せざるを得ません。
さらにあまり知られていませんが、法的義務もあります。刑法には「保護責任者遺棄罪」があり、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしない場合は犯罪になります(刑法第218条)。最近では、介護が必要な実母を公園に置き去りにして死亡させたとして、息子が保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されました(2023年11月30日)。
このように、内には道徳心が、外には法的義務があるために、家族は親や配偶者を介護せざるを得ません。その結果、介護離職が生まれます。家族に犠牲を強いないために、私たちはどうすればよいのでしょうか。解決のヒントをスウェーデンの長谷川佑子さんに求めたいと思います。(宮本礼子)
スウェーデンでは親子でも介護は希望する場合のみ
スウェーデンでは介護離職はありません。その理由を説明します。
スウェーデンでは、パートナーや親子であっても、介護は介護する側が希望する場合にのみ行われます。そして、終末期においては、家族や大切な人と最期を共に過ごすために、医師が終末期ケアと認定することで、給料の8割が社会保障制度から出ます。さらに、自宅でも施設でも病院でも、ケア(医療と介護)はスタッフが行うため、家族は自分が大切な人と過ごしたいと思う時間にいることができ、何かしなくてはいけないことはありません。
18歳以降は親子でも自立した関係
スウェーデンと日本では、家族に対する考え方や社会システムが大きく違います。子どもは高校卒業と同時に大人として認められ、多くの子どもは実家から離れて生活を始めます。大学に行くことになっても学費はかからず、生活費(月8万円支給され、さらに10万円の奨学金が受けられる)も国が支援します。そのため、18歳以降は親子であっても、自立した大人同士の関係になります。
例えば、義理の父(スウェーデン人)が一過性の脳 梗塞(こうそく) で救急搬送された時も、本人は病院で体調がよくなってから夫に電話してきました。自分のことは自分でしたいという考えのようです。普段、一緒に食事をしたり、孫と遊んでくれたり、とても親しい間柄と思っていたので、あまりにもドライな関係に驚きました。
文化や考え方は、人々の生き方や環境により何世代にもわたって形成されるものです。他国の者からは理解し難いこともありますが、それぞれの価値観を尊ぶべきと考えます。
高齢者介護・保護の責任は市町村
スウェーデンでは、親を介護する義務は法律になく、親の介護は「完全なる子どもの自由意思」です。また、「社会福祉法」には、「高齢者介護・保護は社会福祉を担う市町村の責任で行われる」とあり、家族はその責任を求められません。しかし、病気の子どもは親にケアされる権利があり、親は社会保障費をもらって入院中の子どもに付き添います。
このように、「介護離職」のない国では、親は子どもに頼らずに社会保障を得て高齢期を生きていく覚悟が必要です。私がスウェーデン人の同僚に「将来、娘におみそ汁くらいは作ってもらいたいな」と言ったら、「彼女がしたければね」と言われました。「親だからといって作ってもらえる国ではない」と、今から心しておく方がよいということです。
スウェーデン人は、長年税金を払い続けてきたのだから社会保障は権利であると、保障を受けることに堂々としています。そして、国の政策を信頼しています。そのため、家族に頼ろうという姿勢の高齢者には出会ったことがありません。高齢者はみな「自分らしい人生をできるだけ自分の力で送りたい。できないことは公共の支援を使い、自分のことは自分で決めたい」と言います。(長谷川佑子)
両国の法律と国民性に大きな違い
高齢者の介護義務に関する両国の法律は正反対です。日本では、保護する責任のある者が保護を怠れば犯罪になりますが、スウェーデンでは高齢者介護・保護は社会福祉を担う市町村の責任です。そのため、日本の法律は介護離職の要因になりますが、スウェーデンの法律は介護の犠牲者を生みません。日本の法制度は見直す必要があるのではないでしょうか。
その他に、両国には自立心という国民性の違いがあります。日本の親は「老後の面倒は子どもが見て当たり前」と子どもに頼りがちです。例えば、認知症の親の中には、不安になると昼夜を問わず、一日に何十回も子どもの家や職場に電話をかけてくる人がいます。そのため子どもはノイローゼ状態になります。親は認知症になる前から、子どもに頼らないで生きていく覚悟が必要です。
国によって、高齢者介護のあり方と高齢者の心構えがこんなにも違うことに驚きます。超高齢社会を上手に乗り越えるために、日本は発想の転換が必要かもしれません。(宮本)

高齢者介護に森田療法の視点を──「不安と共に生きる」実践が支える現場
日本が世界でも類を見ない超高齢社会を迎える中、介護の現場では日々、多様な課題と向き合う努力が続いている。身体機能の低下、認知症、孤独感、そして人生の終末期に向けた精神的な不安。こうした高齢者特有の問題に対して、注目されているのが日本発祥の心理療法「森田療法」だ。
森田療法は、大正時代に精神科医・森田正馬によって体系化された。「あるがまま」「行動本位」「生の欲望への信頼」などを柱とし、不安や苦しみを排除しようとするのではなく、それを抱えながら生活を営むというアプローチが特徴である。
この考え方が、いま介護の現場で求められている「心のケア」に合致しているという。
「変えられない現実」とのつきあい方
高齢者の多くは、加齢による心身の衰えに直面し、これまでの生活を維持することが難しくなっていく。「もうできない」「迷惑をかけているのではないか」という思いが強まると、自信喪失や抑うつ的傾向が強まる傾向がある。
しかし、森田療法の考え方に基づけば、「不安や不快をなくそうとすること自体が、かえって苦しみを深める」という視点が導かれる。その代わりに、「不安はあるが、できる範囲で日々の生活をこなす」という実践が重視される。
ある介護施設では、入居者に生活記録をつけてもらう取り組みが始まっている。日々の行動を淡々と記録し、定期的に振り返るだけのシンプルな方法だが、自分のペースで生きているという実感や達成感につながっているという。
介護者のメンタルヘルスにも有効
森田療法の視点は、高齢者本人だけでなく、介護を担う家族や専門職にとっても大きな支えとなる。
介護は長期化しやすく、精神的・身体的な負担が大きい。とりわけ、感情的な疲労や「うまくできていないのでは」という罪悪感に悩まされるケースも少なくない。
こうした中、「不快な感情は自然なもの」と認めた上で、それに引きずられすぎずに日々の行動を積み重ねるという森田療法のアプローチは、介護者のストレス軽減や自己理解にもつながるとされている。
介護職員を対象とした森田療法的セルフケア研修も、今後の自治体での導入が期待される。
高齢者の「生の欲望」に着目する支援
森田療法では、人間の根底に「生きたい」「役に立ちたい」といった“生の欲望”があると考える。そのため、「できないこと」よりも「やりたいこと」や「意味を感じる活動」に焦点を当てた支援が推奨される。
これは、介護予防や地域包括ケアの文脈でも有効である。たとえば、週に一度の畑作業、小さな手工芸、食事の配膳など、些細に見える活動が、高齢者の自己効力感や生きがいを支えている。
今後の展望──「語る文化」への回帰
森田療法には「記録」や「観察」の手法が含まれており、当事者研究との親和性も高い。高齢者自身が自らの老いや不安、生きづらさを語り、整理することで、自分の人生に意味を見出すプロセスが生まれる。
一部の地域では、「老いを語る会」や「生活記録ワークショップ」が始まりつつあり、高齢者の内面的なケアを補完する新たな試みとして注目されている。
「老いを語る会」ー特に中高年~高齢者を対象とした「老いと向き合う」体験交流形式の集まり
実施内容として
参加者が「老い」について自由に語る
老いによって強まる「死への不安」「孤独感」「身体の衰え」にどう向き合うかを共有
症状日記や生活記録をもとに、自らの体験を森田的に再解釈する
特徴として
「症状を追わず、目的に立ち返る」森田療法の基本に立ち返る構成
「死の受容」ではなく「生の欲望をどう表現していくか」に焦点がある
医療者や専門家が主導するのではなく、当事者主体の「語り」に重きを置く
「生活記録ワークショップ」ー死と老いに向き合う森田療法の視点を通じて
内容として
週1回、生活日記や過去の思い出を記録する時間を設ける
感情や身体の不調も含めて、記録→共有→受容→行動への転換、というプロセスを導入
目的として
抑うつ傾向のある高齢者に対して「症状中心の思考」を緩める
「書くことで客観視」「話すことで目的に立ち返る」場の提供
森田療法的ワークショップの今後の可能性
「終活」や「回想法(ライフレビュー)」と結びつけた森田的ワークショップの展開
当事者研究の方法論を取り入れ、「自分史のなかで症状とどう付き合ってきたか」を語り合う実践
福祉・介護職向けのセルフケア研修の一部として、高齢者との対話の素材としての「生活記録」活用
終わりに──「死を準備する文化」としての森田療法
高齢者介護は、必然的に「死」に向き合う営みでもある。森田療法は、死への不安を否定せず、それと共に日常生活を積み重ねていく態度を重視する。この姿勢は、古くからの日本的な死生観とも共鳴する部分が多い。
「死に向かう」ことを「生ききる」こととして支える。森田療法は、そうした“文化としての介護”の地平に、新たな道筋を示しているのかもしれない。
付記ー回想法(ライフレビュー)について
回想法(ライフレビュー)とは、高齢者が自分の過去の体験をふり返りながら語ることで、心の整理をし、生きる意味や価値を見出していく心理的な方法である。
■ どんなことをするの?
昔の写真や手紙、道具などを見ながら話す
「子どものころ、どんな遊びをしてた?」
「結婚式の日はどんな気持ちだった?」
「一番つらかった時期を、どう乗り越えた?」
といった質問に答えるような形で、自由に語ってもらう
■ なぜいいの?
自己肯定感が高まる
「あんな苦労も乗り越えてきた」と振り返ることで、自分に自信が持てる孤独や不安の軽減
誰かに話を聞いてもらうことで、つながりや安心感を感じられる認知機能の刺激になる
記憶をたどることが、脳へのよい刺激になり、認知症予防にも役立つ人生の意味づけが進む
「自分の人生には意味があった」と感じられるようになる
■ 森田療法との接点は?
森田療法では「あるがまま」「今ここを生きる」ことが大切
回想法も、「過去の出来事を再評価しつつ、今の自分を受け入れる」ことを目指す点で、とても親和性がある
とくに「不安や後悔を否定せず、語ることで整理する」作業は、森田療法の“感情の自然な流れを妨げない”という考えに合致する (以上)