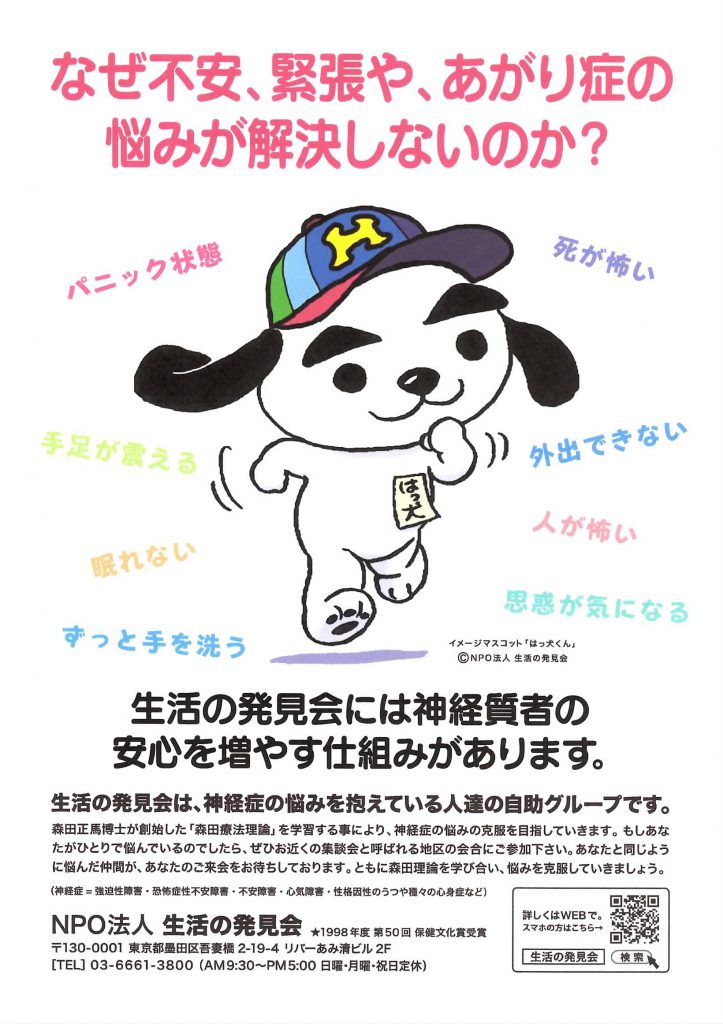森田療法が目指す神経症ってなんだろうー大田集談会でのお話しに補足してー
神経症とは?
私たちは日々の暮らしの中で、「緊張する」「不安になる」「失敗したくない」といった感情を感じることがあります。これはごく自然なことです。でも、こうした感情を「いけないもの」「異常なこと」と思いこんで、なんとか消そうと頑張りすぎてしまうと、かえってその感情が強くなり、生活に支障をきたしてしまうことがあります。これが「神経症(しんけいしょう)」と呼ばれる状態です。
神経症は、病気というより、心のクセや考え方の傾向によって生まれる心の状態です。脳や体の病気(器質的な病気)ではありません。
たとえば、人前で話すときに緊張して「うまく話せないかもしれない」と不安になるのは、誰にでもある自然なこと。でも、それを「異常だ」「絶対に緊張してはいけない」と思いこむと、「どうしよう、また緊張したら…」という不安が頭から離れず、そのことばかりが気になってしまいます。このように、不安にとらわれることで症状が作られていくのです。森田療法では、これを「とらわれ」と呼びます。
◆ 神経症になる背景には何があるの?
神経症になりやすい人には、いくつかの共通した傾向があります。
- うまくいかない現実に対する不安(=適応不安)
生活の中で、思うようにいかないことや虚しさ、挫折感があり、それが心の奥でストレスになっています。 - 感じやすく、まじめな性格
森田療法では、こうした人の特徴を「ヒポコンドリー性基調」と呼びます。これは「まじめで責任感が強く、不安を感じやすい心の土台」のことです。
◆ なぜ症状が強くなるのか? 〜心のメカニズム〜
神経症が進んでいく背景には、いくつかの心の動きがあります。
- 思想の矛盾(理想と現実のズレ)
「こうありたい」と思う自分の理想と、「実際の自分」との間にズレがあると、人は苦しくなります。このズレが、「なんとか理想の自分にならなくては」と過剰な努力を生み、それがとらわれの元になります。
- 精神交互作用(注意が不安を大きくする)
「緊張してはいけない」と強く意識するほど、「また緊張してきた」と不安が強くなり、さらにその不安に注意が向き…と悪循環に陥ります。このように、注意と感覚が影響しあって、不安や違和感が大きくなってしまうのです。
- 不安の固着(不安が生活の中心になる)
不安が強くなると、「この不安があるから何もできない」と思い込み、不安がすべての原因だと考えるようになります。そして本来の生活や目標に意識が向かなくなります。
- 実生活上の悪循環
症状が出そうな場所を避けることで、一時的には楽になりますが、その場所がますます怖くなり、ますます行けなくなる。こうして、生活範囲が狭まり、社会生活も後退していきます。
◆ では、どうすればいいの?
■ 森田療法が目指すところ
森田療法は、不安を「なくそう」とはしません。
不安や緊張は、人間として自然な感情であり、それを無理に消そうとすることが、かえって苦しみを生んでしまうのです。
森田療法の考え方はこうです:
- 不安や恐怖を感じながらも、それを抱えたままでも「必要な行動はできる」ということを、実生活の中で少しずつ体験していく。
- 「不安をなくすこと」ではなく、「不安とともに生きること」を学ぶ。
- そうすることで、自分の中にある「本当はこう生きたい」という力(生の欲望)に気づき、前に進むことができるようになります。
◆ 森田療法の実践ポイント
- 不安や恐怖は感じてもいい。それを排除しようとせず、「そう感じている自分」を受けとめていく。
- 症状があっても、それにとらわれずに必要な行動をすることで、生活が少しずつ回復していく。
- こうして、「神経症」は、自分らしく生きていくためのひとつのきっかけになることもあります。
森田療法のメッセージ:「生の欲望」に耳をすます
森田療法では、症状の背後にある「生きたい」という根源的な力(=生の欲望)に気づくことが大切だとされています。
それは、ただ症状をなくすこと以上に、「自分の命をどう生きるか」に直結した問いです。
- 不安があってもいい。
- 恐怖があっても、自分の人生を歩いていける。
- 完全でなくていい。でも、生きたいという気持ちは、確かにそこにある。
この考え方は、人生は「治す」ものではなく、「生きる」ものだという深い人間観に根ざしています。
まとめ:不安を敵にせず、人生を味方につける
- CBTは、思考を味方につけて人生を切り開く「理性の道」。
- 森田療法は、不安も味方にして生きる「自然の道」。
どちらも、苦しんでいる人にとって有効なアプローチですが、森田療法には、「生きることの味わい」や「不完全さを受け入れる深さ」があります。
人生論として見たとき、それはとても東洋的で、静かだけれど確かな灯のような道しるべとなります。
「生きたい」という声に耳をすます
——森田療法が教えてくれること
年齢を重ねると、「これから自分はどう生きていけばいいのか」とふと立ち止まることが増えてきます。身体の変化、人間関係の移り変わり、あるいは仕事や役割を終えた後の空白。そんなとき、不安や迷いが心を覆い、「こんなはずじゃなかった」と、自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、森田療法はそんな私たちに、静かに語りかけてくれます。
「不安があってもいいんですよ」と。
「恐怖があっても、自分の人生を歩いていけるんです」と。
森田療法の中心にあるのは、「生の欲望」という言葉です。ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、これは私たち誰の心にもある、「もっとこう生きたい」「前に進みたい」という、根っこの力のことです。たとえ不安で足がすくんでも、その奥には確かに「生きたい」という想いがある。それに気づくことが大切だと、森田療法は教えてくれます。
不安や恐怖を取り除こうとすればするほど、かえってそれが大きく感じられてしまう。でも、「ああ、私は今、怖いんだな」「不安なんだな」とそのまま受け止めて、できることを一歩ずつやっていく。そうすると、少しずつ心がほぐれてきて、自分なりの歩き方が見えてきます。
誰もが完璧ではありません。だからこそ、「不完全なままでも、自分らしく生きていい」と思えたとき、人は年齢に関係なく、もう一度、自分の人生に灯をともすことができるのです。
これからの生き方に正解なんてありません。でも、不安を抱えながらも、「それでも生きたい」という小さな声に耳をすませながら歩いていけば、その道のりは、きっとあなただけのかけがえのない人生になるはずです。
ミニマリストの午後に(下丸子土曜集談会からの歓迎メッセージ)
年を取るってことは、なんというか、余分なものがひとつずつ剥がれ落ちていくプロセスみたいなものだと思う。昔は気になって仕方がなかったことが、ある日ふと、まるで海辺に打ち上げられたクラゲみたいに、どうでもよくなる。あの時の不安も、嫉妬も、焦燥感も、ぜんぶ持ってはいるんだけれど、それが自分の「全部」じゃないってことが、やっと体の奥のほうで納得できるようになる。
ミニマリズムという言葉がある。ぼくはそれを、部屋のインテリアとか、持ち物の数の話にとどめておくのはもったいないと思っている。あれはむしろ、生き方の問題だ。心の中にも、何かを削ぎ落としていく必要がある。いや、正確に言えば、削ぎ落とすんじゃなくて、手放していくんだ。持っていてもしょうがない執着とか、変えようとしても変わらない気分とか、そういうものを「まあ、いてもいいけど、べつに主役じゃないよね」と、片手間に飼っておくこと。それがミニマリズムの核なんじゃないかと思う。
森田療法という日本の精神療法がある。「あるがままに」とか、「感情は自然にまかせて、行動は目的本位に」とか、いくつかの原則があるんだけれど、要するに、「感じてもいいけど、それで立ち止まらなくていいよ」という生き方だ。不安があるならそのままにしておく。不安を消そうとしない。不安があっても、やることはやる。そうしているうちに、不安がひとりでに立ち去っていくこともあるし、ずっと一緒にいることもある。でも、どっちでもかまわない。
高齢になって、体の動きは鈍くなるし、昔みたいに要領よくもいかない。だけど、そのぶん、ものごとの「流れ」を見極める力は、少しだけ育ってくる。自然のリズムみたいなものを、体の皮膚越しに感じるようになるんだ。そういうとき、ぼくらはもう「なにかになろう」とか「もっと良くなろう」とか、そういう力みに疲れてくる。そして代わりに、「もう、これでいいんじゃないか」と思う。
不安を抱えたまま、それでも静かに日々を営んでいく。感情を無理に変えようとせず、行動を淡々と続ける。季節が巡るように、自分も自然の流れの中にあることを信じて、身をまかせる。そんなふうに歳を重ねていけたら、人生って、案外悪くないんじゃないかと思う。
春の午後、コーヒーを淹れて、窓の外の光をぼんやり見ている。風に揺れるカーテンの動きにさえ、なんだか少し、救われたような気がしてくる。