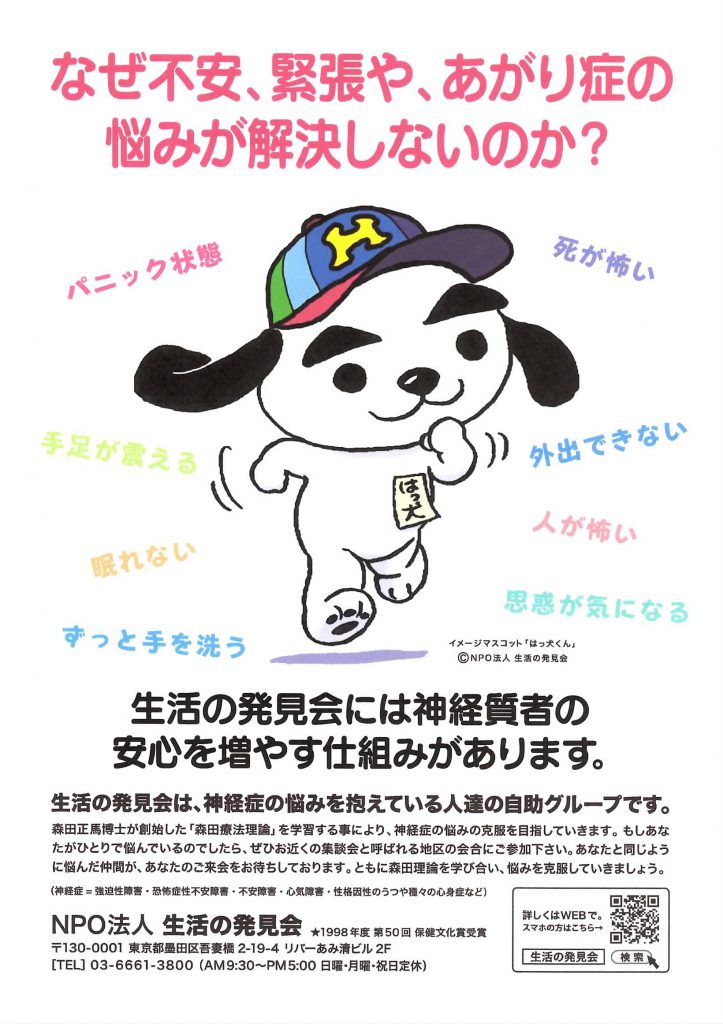神経症という名の駅で
ある雨の月曜日、僕は決まった時間に目を覚まし、決まった順番で歯を磨き、コーヒーを淹れ、そしてふと思ったんだ。「今日、僕は世界にちゃんと適応できるんだろうか」と。
それは突拍子もない考えじゃなかった。ここ数週間、いや正確に言えば数ヶ月、僕の内側には小さなざわめきがあって、それがまるで駅のベンチで眠れずに震えている旅人のように、居場所を求めてさまよっていた。
僕は32歳の翻訳家で、東京郊外のアパートにひとりで暮らしている。表面的にはそれなりに安定している仕事で、誰にでも優しくできる程度の余裕もある。だけど、それはあくまで「外側の話」だった。
内側では、ある種の虚しさが僕の肩にひっそりと乗っていた。いつからかは覚えていない。翻訳の仕事をこなし、メールを返し、夜はパスタを茹でて映画を観る。そんな日々のなかで、何かがうまく嚙み合っていない感覚だけが静かに残った。
背景にある適応不安
原因ははっきりしない。だけど、森田療法の本にあったように、「生活のどこかにある、思うようにならない現実」が、僕のどこかを圧迫していたのだと思う。
例えば、誰にも相談できなかったこと。自分の将来がぼんやりしていること。恋人と別れたあの夜に感じた、空の深さと孤独の広がり。そんな断片的な出来事が、知らぬ間に「適応不安」という形で僕の精神を締めつけていたのかもしれない。
ヒポコンドリー性基調という素質
さらに、僕にはその「不安」を特別な形で受け取る素質があったらしい。森田正馬はそれを「ヒポコンドリー性基調」と呼んだ。
要するに、感じすぎてしまう心だ。たとえば身体のちょっとした違和感が、病気の始まりではないかと不安になるように、僕は「うまくいっていない生活」そのものが、まるで病のように思えてくるのだ。
真面目に生きたい。ちゃんとした人間でいたい。だけど、現実はそう簡単じゃない。すると僕は、「どうしてうまくできないんだ」と自分を責め、そこにさらに不安が雪のように降り積もっていく。
そして、症状が現れる
ある朝、僕は駅のホームで電車を待っていた。心臓がバクバクしていた。息がうまく吸えない。目の前の空気がゆがんで見える。——そう、それが「症状のはじまり」だった。
もちろん、医者に行っても異常はなかった。だけど僕の中では、明確に「何かが壊れた」という実感があった。
それから僕は、「症状を何とかしなきゃ」という焦燥に取りつかれ、ますます不安の迷路に迷い込んでいく。それはまるで、出口のない駅構内をぐるぐると歩き回っているような感覚だった。
この物語は、僕の話でもあり、誰かの話でもある。神経症という駅には、きっとたくさんの人が立ち止まっている。そして、その多くは、ただ「真面目に、ちゃんと生きたい」と願っているだけなのだ。
神経症という名の駅で
― 症状が、僕になるまで ―
窓辺に置いた観葉植物の葉が、春の光をうっすらと反射している。
けれど、僕の中には未だに冬の名残のようなものが張りついていた。あの駅で感じた動悸、手の震え、呼吸の浅さ。それらは一度去ったかのように見えて、再び、日常のすき間から静かに這い寄ってくる。
僕は「また来た」と思った。
そして、同時に「どうにかしなくては」と思った。
それが、症状の罠だとも知らずに。
■ 思想の矛盾 ―「こうあるべき」と「そうじゃない僕」
僕は、自分のことを「ちゃんとしている人間」でありたいと思っていた。
締切を守り、礼儀を忘れず、メールには即レスを返す。誰かが困っていれば手を差し伸べ、いつも「冷静」でいたい。
だけど現実の僕は、駅のホームで胸を抑え、知らない誰かの視線に怯え、予定していた仕事に手がつかず、気がつけば朝から布団の中で天井を見つめていた。
理想の自分と、実際の自分とのズレ。
そのギャップが僕の中で「ねじれ」を生んでいた。
僕は自分を「そうであるべきもの」に無理やり近づけようとして、
「そうでない自分」を許すことができなかった。
それは、見えないハーネスで自分の心を締め付けるような苦しさだった。
■ 症状の発生と固着 ―「それがあるから、自分はダメなんだ」
そして、決定的な転換が起こる。
「この違和感をなんとかしないと、自分はもうまともに生活できない」と思い込むようになった。
いつしか、僕の生活の中心には「症状」が鎮座していた。
朝起きて、まず症状を探す。
仕事を始めても、うまくいかない原因を症状のせいにする。
人と会えば、「こんな状態で大丈夫だろうか」と考える。
不安という一点に、すべての光と影が集まってしまったのだ。
本来、不安は人間にとって自然な感情だ。
それがまるで“敵”のようになってしまったとき、僕の中で「神経症」という名の風景が完成した。
■ 恐怖の回避と、実生活の後退
次第に、避ける対象は「駅」だけではなくなった。
人混み。会話。知らない人の視線。納期のある作業。
“症状が出そうな気配”がするもの全てから、僕は一歩ずつ身を引いていった。
最初は「無理をしないこと」と思っていた。
けれど、それはいつしか「何もしないこと」に変わっていった。
生活は静かだった。
でもその静けさの中には、どこかに閉じ込められたような息苦しさがあった。
やらなくてはならないこと、会わなければならない人、
作らなければならないものが、そこにあると知っていた。
でも、それが見えなくなっていった。
恐怖の厚い膜が、それらの輪郭を覆ってしまったからだ。
■ 葛藤 ― よりよく生きたいという願い
それでも、心のどこかには、
「本当はこんなふうに生きたいわけじゃない」
という声が、確かにあった。
誰かに必要とされたかった。
自分の言葉や表現が、誰かの心に届く瞬間が欲しかった。
翻訳の仕事も、創作も、生活も——
本当は、全部、ちゃんとやっていきたかった。
けれど、そこに近づくたびに、症状が牙を剥いた。
前に進もうとするたびに、引き戻される。
まるで、心の中で一人、綱引きをしているようだった。
■ それでも、生きている
ある日、ふと、森田療法の言葉が心に留まった。
「あるがまま」——
不安があるなら、不安のままにしておけばいい。
症状を消そうとする努力こそが、症状を育ててしまうのだと。
その夜、僕はベランダでコーヒーを啜りながら、不安と並んで座っていた。
決して消えない感覚。
でも、それでも「今日は翻訳の途中まで進めたじゃないか」と、自分に言ってみる。
「恐怖があるなら、そのままにして、やるべきことをやる。」
え? そんな馬鹿な、と思った。
怖いから逃げているのに、そのままでいいとは?
でも、ふと気づいた。
今までの僕は、「症状を消してからじゃないと動けない」と思い込んでいた。
だけど実は、
「症状があっても、生きられるのではないか」
という道もあるのかもしれない。
たぶん、これが始まりだと思った。
治そうとするのではなく、「それがある人生をどう生きるか」を考える日々の。
そしてまた次の朝、僕は電車に揺られながら、少しだけ心が軽くなっているのを感じた。
不安はそこにあったけれど、それは僕を止めるものではなかった。
■ それでも僕は創る
不安は僕から離れていなかった。
けれど、創作もまた、僕の中にあった。
不安があるまま、筆を持つ。
違和感が残る体で、言葉を紡ぐ。
逃げるのではなく、
ただ「やるべきこと」を、今日という一日の中に置いておく。
そんなふうにして、僕は少しずつ、「生き直し」を始めていった。
― あるがままの線路を歩く ―
春の終わりが近づくころ、僕はふたたび小さなアトリエに戻ってきた。
窓辺の観葉植物は、少し葉を伸ばしていた。僕が立ち止まっていたあいだにも、世界は少しずつ進んでいた。
症状は、まだ僕のそばにいた。
だけど、もう敵ではなくなっていた。
■ 不安は「消すもの」ではない
森田療法の考えに出会ってから、不思議と力が抜けた。
「不安をなくすのではなく、不安のまま、生きていく」。
そんな逆説的な言葉が、妙に心に馴染んだ。
不安というのは、そもそも人間に備わっている大切な感情だった。
大切なことを大切にしたいと思うからこそ、不安になるのだ。
そう思ったとき、症状に振り回されていた日々が、少しずつ別のかたちに見えてきた。
僕はただ、「真剣に生きたかった」だけだったのかもしれない。
■ ほんとうの自分に気づく旅
森田療法の学びを重ねていくうちに、
僕は自分の中にある「適応不安」に気づくようになった。
――誰かにとって役に立ちたい。
――創作を通して、人とつながりたい。
――生きている意味を実感したい。
そんな素直な願いが、症状の奥に静かに隠れていた。
そして、驚くほど自然に、僕の中に「やりたい」という力があることにも気づき始めた。
不安に負けていたのではない。
不安の奥に、大事なものがあったのだ。
■ 行動によって「できる」を体験する
だから僕は、また駅に行った。
手が震えながらも、次の翻訳案件の打ち合わせに向かった。
頭が真っ白になりそうになりながらも、新しい短編のアイデアを書き留めた。
うまくいったとは言えない。
でも、できなかったことを“やった”という事実だけが、僕を少しずつ変えていった。
不安があっても、生活はできる。
恐怖があっても、必要なことはできる。
その「実感」が、薬でもなく、誰かの助言でもなく、自分の足で築いた小さな証だった。
■ あるがままの自分と生きていく
不安、恐怖、悩み――
それらは今も、ときどき僕の前に立ちはだかる。
でも僕は、それらを追い払おうとはしない。
ただ「また来たな」と言って迎え入れ、「一緒に行くか」と肩を並べて歩く。
あるがままの自分。
完璧ではない、でもどこかで誠実な自分。
森田療法が目指すのは、そういう生き方なのだと今では思う。
■ 最後に残ったもの
夜、原稿の文字を打ちながらふと手を止めて、
あの駅のホームの風景を思い出す。
当時は、そこが「終点」のように思えていた。
けれど今は違う。
そこは、始まりの駅だったのかもしれない。
そして今も、不安を抱えながら、僕は電車に乗っている。
少しだけ強くなった手で、行き先の違う切符を握りしめながら。