エンドオブライフと生きること・見送ることの意味
人は、いつか必ず命を終える。そのことを、私たちは頭では知っている。でも、日々の暮らしのなかで「死」と向き合うことは、そう多くはない。
けれども、家族や友人の終末期に寄り添うとき、あるいは自分自身の老いを実感するとき、「エンドオブライフ(人生の終わりの時期)」という言葉が、急に現実味を帯びて目の前に立ち現れる。
誰もが通る道。けれども、そこにはそれぞれの人生の色と想いが刻まれている。
病気が進み、治癒が難しいと告げられたとき、人は何を思うのだろう。
「まだやり残したことがある」
「誰に何を伝えたいだろう」
そんな問いが、静かに心の中をめぐる。
この時期に大切なのは、決して「どう死ぬか」だけではない。むしろ、「どう生き切るか」なのだと思う。
一日一日が、かけがえのない時間になる。
当たり前だった朝の光が、窓辺の風が、愛しい人の声が、これまで以上に鮮やかに感じられる。
そして、誰かのそばでその時間に寄り添う者も、また同じように、命の重みを感じている。
見送るということ。それは、別れの痛みであり、同時に、感謝と愛を形にする営みでもある。
私たちは、誰かを見送るとき、自分の中にも小さな変化が起きていることに気づく。
その人の言葉や笑顔が、ふとした瞬間によみがえり、自分のこれからの生き方に影響を与えてくれるのだ。
「私は、あの人のように生きられるだろうか」
「今の自分のままでいいのだろうか」
そんな問いが心に芽生えたとき、私たちはもうすでに、命のバトンを受け取っているのかもしれない。
森田療法では、「あるがままに生きる」ことの大切さが説かれている。
不安も悲しみも、人間として自然なもの。
それを無理に消そうとせず、そのままにして、自分のなすべきことに目を向ける。
死にゆく人も、見送る人も、残された時間をどう過ごすかは、「今をどう生きるか」にかかっている。
過去でも未来でもない、今この瞬間にこそ、命は宿っている。
エンドオブライフを見つめることは、決して絶望ではない。
それは、今を丁寧に生きるための、深い問いかけなのだ。
人は皆、誰かに見守られ、誰かを見送りながら、生きていく。
その循環の中で、命の意味は静かに輝き続けている。
エンドオブライフと生きること・見送ることの意味
私たちの機関誌『飛翔』によせられたメンバーの一人の手記を許可を得て掲載いたします。
「私の母は、静かに人生の終わりを迎えた。
八十六歳。長く糖尿病を患いながらも、自分のことは最後まで自分でやりたいと言い張る、芯の強い人だった。最期の半年は病院ではなく、古くて風通しのよい自宅で過ごした。医療的には回復の見込みがないと聞かされていたが、それでも母は、「今日がいちばん大事なんだよ」と笑った。
朝の光が差し込む縁側で、小さな鉢植えの世話をしながら、母はしきりに昔の話をした。幼いころの私が庭で転んで泣いていたこと、父と喧嘩して一晩口をきかなかったこと、戦後の苦しい時代をどう生き抜いたか…。どの話も、淡々としていて、でも確かに生きてきた重みがあった。
ある日、母がぽつりとつぶやいた。
「見送るって、ただ悲しいだけじゃないのよ。私ね、おばあちゃんを見送ったとき、“ああ、自分もちゃんと生きなきゃ”って思ったの。いのちを渡された感じ。そういうのって、あるのよ。」
私はその言葉を、今でも大切に覚えている。
母を見送ったあと、私の生活は何もかもが「母のいない風景」になった。
けれど、そこには不思議と、温かい記憶があちこちに残っていた。
食卓の椅子、使い古した急須、裏庭の紫陽花。どれもが、母の時間を吸い込んで、今もそこにある。
悲しみは確かにあった。でも、ただの喪失ではなかった。
むしろ、母が最後に見せてくれた「生き切る姿勢」は、私にとっての道しるべになっていた。
森田療法では、「死の不安」は自然なものであり、それを無理に抑えずに、その中でできることをする――という考えがある。
母は、まさにそうだった。不安がなかったわけではない。けれどそれを抱えながらも、目の前の一日を慈しみ、小さな楽しみを見つけていた。
それは、“立派なこと”ではなく、ただ静かに、人として当たり前のように生きるという姿だった。
今、誰かを見送ろうとしている人がいたら、私はこう伝えたい。
「その人のそばにいる時間は、かけがえのない贈り物です」と。
そして、自分が見送る側になることもあれば、見送られる側になる日もくる。だからこそ、日々の小さな営みを、大切にしたいと思う。
命は限りがあるからこそ、輝く。
その輝きは、見送ったあとも、私たちの心のなかで生き続けている。」
あるがままに、いのちの終わりと向き合う
――エンドオブライフにおける森田理論の光――
人は、いのちの終わりを前にしたとき、さまざまな思いを抱える。
「もっと生きたい」「まだやり残したことがある」
「この先、痛みはあるだろうか」「家族に迷惑をかけてしまうのではないか」
…そして、「死ぬのがこわい」と。
どれも、人間として自然な感情だ。むしろ、それを感じないことのほうが、不自然なのかもしれない。
私は、森田療法の学びを通じて、この“自然な感情を否定しない”という姿勢に、深く救われた。
森田理論では、死への不安も、焦りも、どうしようもない悲しみも、「あるがまま」として認める。
それを無理に打ち消そうとしたり、ポジティブに上書きしようとしたりしない。
その代わり、「不安は不安としてそこにある」ことを受け入れながら、「今、自分ができることに向かっていく」ことを勧めてくれる。
それはまるで、大きな波の中であわてて泳ごうとせず、ただ浮かんでいるような感覚に近い。
不安や死の恐れがあるのは自然なこと。
でも、それに巻き込まれすぎることなく、「今できること」に静かに目を向けていく。
たとえば、朝の光を浴びること。
家族の手を握ること。
好物をひとくちでも味わうこと。
「ありがとう」と誰かに伝えること。
それらは、どんなに小さくとも、いのちを肯定する行動なのだ。
私は、末期がんの診断を受けたある年配の女性と出会ったことがある。
「私は怖い。正直に言えば、毎日怖い。でもね、それでも布団を干したくなるのよ」と笑った。
彼女は、不安がなくなったわけではない。
ただ、その不安に正面から向き合いながら、「今日やれること」に目を向けていた。
彼女は編み物が得意で、ベッドの上でも毛糸と針を手放さなかった。
「このマフラーが編み終わる頃、私はどうなっているかしらね」と言って、笑っていた。
それは「がんばっている姿」ではなく、「いのちの自然な営み」だった。
私はそこに、森田理論の言う「あるがままの生」と、「生の欲望の流れに従って生きる」という姿勢を見た。
森田療法の核には、「生の欲望」がある。
どんなに弱っても、人は“生きたい”“生ききりたい”という本能的な欲求を持っている。
たとえ死を前にしていても、それは消えることがない。
「不安や苦しみがあるからこそ、人は生きるための行動をする」
――それが、森田理論の深い洞察だ。
だから、エンドオブライフにおいて森田理論を活かすとは、「不安をなくすこと」ではなく、「不安があっても、その人らしく過ごすことを支える」ということなのだと思う。
いのちの終わりは、決して「終わり」ではなく、その人らしさがもっとも濃く現れる時間なのかもしれない。
そしてそれを、「あるがまま」に受け止める力は、最期のときだけでなく、私たちの日常にも静かに光を投げかけてくれる。
「今日を生きる」ということ。
その一歩一歩が、いつかの見送りの瞬間にも、穏やかな意味をもたらしてくれるのだろう。

興味のある記事がありましたので転載いたします。
ー読売朝刊ヘッドライン <newsletter@my.yomiuri.co.jpより転載ー
尊厳死って何? 延命望まぬ人が増えているのに、医療者はその気持ちを理解しない
「尊厳死」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、ピンとこない方も多いと思います。広辞苑によると、尊厳とは「尊く厳かで、犯しがたいこと」です。しかし、何を尊厳と言うかは人により違うので、どのような死が尊厳ある死(尊厳死)かも、人によって違うと思います。
死にゆく高齢者の尊厳は守られているか
誰にでも尊厳があり、特に弱い立場の人の尊厳は、周囲が守ってあげなくてはなりません。しかし、私たちは果たして、死にゆく高齢者の尊厳を守っているでしょうか。私はむしろ、尊厳を犯しているように思います。
医療が発達していなかった時代の死は、単に「死」でした。しかし、医療が進歩して高齢者が延命されるようになると、自然死、尊厳死、平穏死、という言葉が生まれてきました。事実、延命医療が行われていない国では、自然死、尊厳死、平穏死という言葉は使われていません。
寿命が来ても先送りされる死
生き物は、寿命が来ると死ぬのが当たり前です。しかし、人工栄養や人工呼吸器や人工腎臓などを使い、我が国では死が先送りされます。そのため、高齢者は何もわからない状態で生き続け、たんの吸引などで苦しみます。
故中村仁一医師は、「医療の鉄則」を次のように言います。
・死にゆく自然の過程をじゃましない
・死にゆく人間に無用の苦痛を与えてはならない
延命は死にゆく自然の過程をじゃまし、死にゆく人間に無用の苦痛を与えます。延命しなければ、自然に、尊厳を持って、穏やかに亡くなることができます。
日本学術会議は、尊厳死を「過剰な医療を避け尊厳を持って自然な死を迎えさせること」、日本尊厳死協会は「自らの意思で延命措置を断り、自然の経過のまま受け入れる死」と説明しています。
延命を断り、穏やかな死を望む人が増えた
私の入院患者さんで、88歳のアルツハイマー病の女性の例です。自宅で暮らしていましたが、大声でどなり、夜眠らなくなったので当院に入院しました。認知症は進み、夫の顔もわかりませんが、夫は毎日会いに来ました。コロナ禍で来られなくなると、息子が代わりに写真や手紙を送ってきました。
ある日、重度の脳 梗塞(こうそく) を起こし、意識がなくなりました。息子は「以前、先生から、『食べられなくなったら管や点滴で延命しますか』と聞かれた時、母は『そうなったら、もういらないわね』と答えていました」と言います。夫も「食べることができず、何もわからないなら、心臓が動いていても生きているとは言えない。点滴を外してほしい。もう十分してもらいました」と言います。
私は「1週間、点滴しても目覚めなければ、点滴をはずしましょう。」と言いました。しかし、4日後には血圧が下がり、回復の見込みはなくなったので、点滴を中止しました。それから3日後に安らかに亡くなりました。
このご夫婦のように、延命を断り、穏やかに死を迎えることを望む人が増えています。生きる意味を知っているからだと思います。一方、我々医療者は、医学的知識に振り回され、生きる意味がわからなくなっています。その私たちが、患者さんの死をコントロールしてよいのでしょうか。どう死ぬかは本人が決めることです。
自分で考えなくてはならない人生の終わり方
医療が発達したばかりに、自分で人生の終わり方を考えなくてはならなくなりました。確かに、今日のように、延命医療で何年も生き続けたり、濃厚医療で苦しんだりする責任は医療側にもあります。しかし、国民一人ひとりが、自分はどのように生きて、どのように死を迎えたいかを考えないことには、この問題は解決しません。
次回はリビングウィルについて話しますが、尊厳死を迎えるためにはリビングウィルを書き残すという努力が必要です。自然死、尊厳死、平穏死という言葉が不要になる日が待たれます。(宮本礼子 内科医)





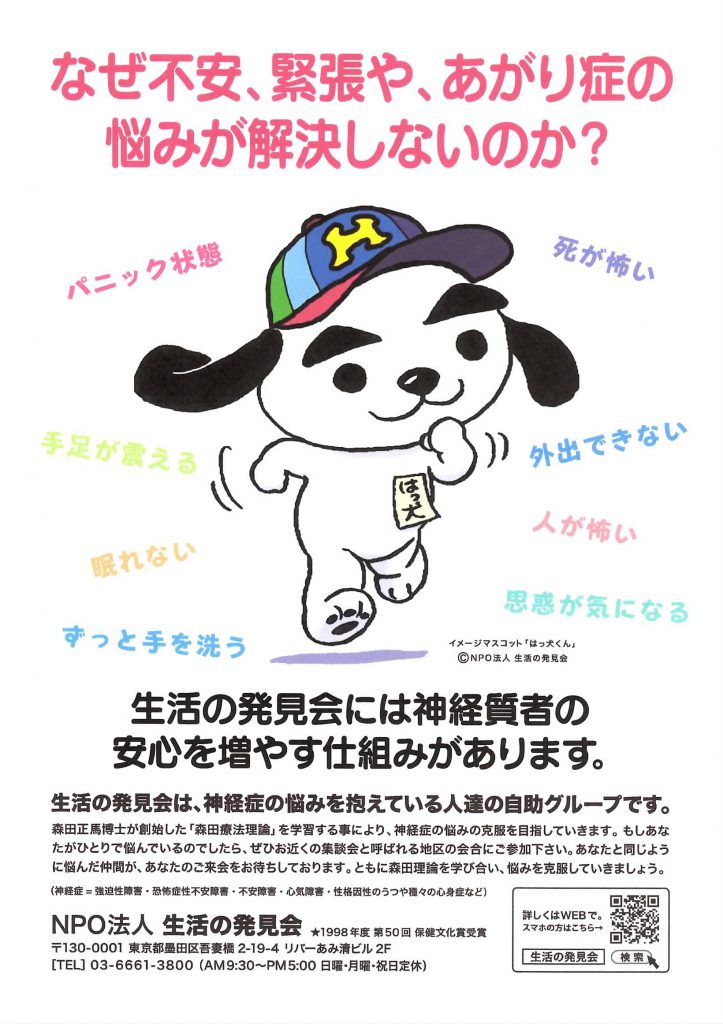












 Not optimized
Not optimized