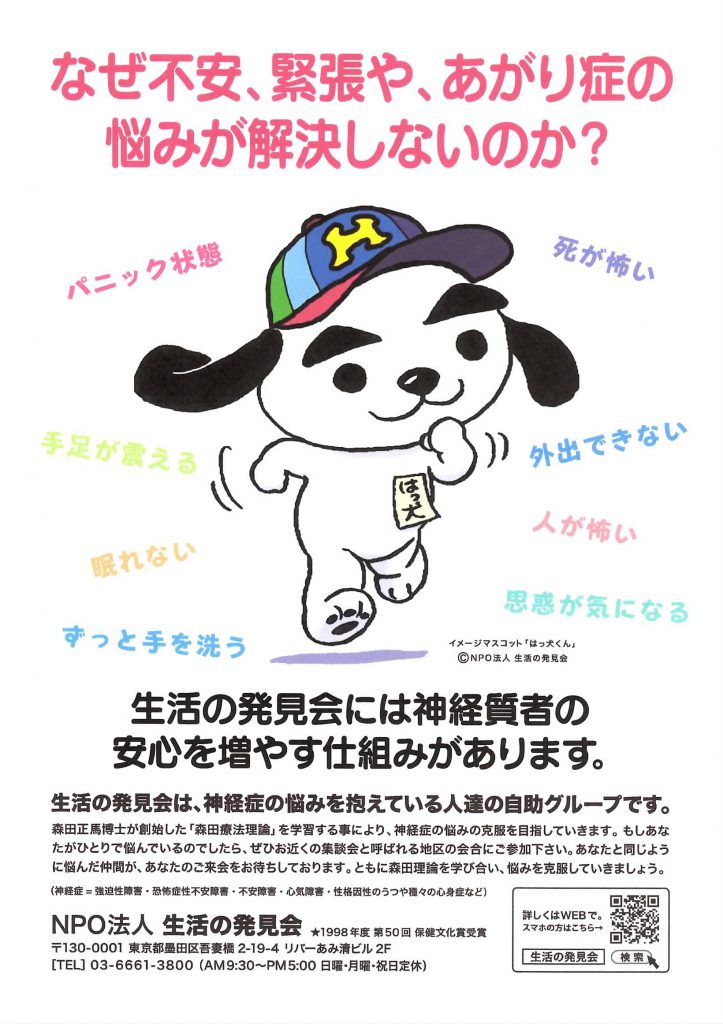あるがままという態度価値の時代変遷
「あるがまま」という態度価値は、時代や文化の変遷に伴って異なる意味や解釈がされてきました。この価値観の変遷について考えるためには、さまざまな社会的、哲学的、宗教的な背景を考慮することが重要です。
1. 仏教における「あるがまま」
仏教において、「あるがまま」という考え方は非常に重要です。仏教では、物事が本来の姿である「無常」として存在し、それを受け入れることが大切だとされています。特に禅宗では、思考や感情をありのままに受け入れることを重視し、無理に変えようとしない態度が修行の一部とされています。このような態度価値は、仏教の教えの中で時間を超えて広がり、現代にも影響を与えています。
2. 近代における「あるがまま」
近代に入ると、西洋の哲学や科学的思考の影響で、物事を理性や論理で捉えようとする傾向が強まりました。合理的な思考や目標志向が重視され、精神的な安定や自然体を重んじる「あるがまま」の態度は、むしろ受動的に映ることがありました。しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、哲学や心理学の分野で自己認識や存在論の問題が再び注目され、「ありのままの自分を受け入れる」という価値が見直されるようになりました。
3. 現代における「あるがまま」
現代では、特に心理学的な観点から「あるがまま」という価値が再評価されています。例えば、マインドフルネスや自己肯定感の重要性が広く認識され、過去や未来にとらわれず、現在の自分をそのまま受け入れることが精神的な健康に良い影響を与えるとされています。現代のライフスタイルや社会的な圧力が強調される中で、他者との比較を避けて自分を大切にする姿勢が重要視されるようになりました。
4. 「あるがまま」の価値の変化
時代を経て、「あるがまま」という価値は、受け入れの態度、自己肯定、さらには社会的な調和を追求する意味を持つようになりました。しかし、社会の進化や個人主義の高まりに伴い、「あるがまま」をそのままにしておくことが必ずしも適切な価値観ではなくなった局面もあります。個々人が自分をどう育て、成長させるかという問題が大きくクローズアップされ、自己改善や変化の重要性が強調されるようにもなっています。
日本文学史からとらえたあるがままの概念について
日本文学史から「あるがまま」という概念を捉えると、その価値や意味が時代ごとにどのように変遷してきたかが見えてきます。この概念は、特に日本の宗教、哲学、そして文学の中で重要な役割を果たしており、時代背景により異なる解釈がされています。
1. 古代から中世にかけての仏教的背景
日本において「あるがまま」の考え方は、仏教の影響を強く受けています。仏教は、物事の無常や、存在そのものをありのままに受け入れることを教えます。この影響は日本文学においても色濃く表れ、特に中世の文学においては、仏教的な無常観が作品にしばしば反映されます。
例えば、『平家物語』のような歴史物語では、栄華や権力の無常さがテーマになっています。栄枯盛衰の美しさを称賛し、物事の本質をありのままに受け入れ、過ぎ去る運命を無常に感じることが文学的な美学として表現されています。ここでは「あるがまま」が、無理に変えようとせず、流れに従うことの美しさとして現れます。
また、禅僧の詩や書状にも「あるがまま」を受け入れる心境が表現されています。禅の思想では、「無心」や「今ここ」の意識が重視され、ありのままの自分を受け入れる態度が、文学にも影響を与えました。禅僧が書いた詩や書には、無駄のない簡潔さと、物事の本質を見極める深い洞察が込められています。
2. 近世文学における「あるがまま」
近世に入ると、浮世草子や和歌、俳句などで、「あるがまま」の美学が発展します。江戸時代の文学は、庶民文化の栄華を背景に、多様な価値観が反映されています。
松尾芭蕉の俳句では、「あるがまま」の概念が深く根付いており、その作品には、自然のありのままの美しさを称賛するものが多くあります。芭蕉は、日常の中の素朴な瞬間や、自然界の些細な変化に美を見出し、過剰な修飾を排したシンプルな表現を通じて「無駄を省いたありのままの美」を追求しました。例えば、「古池や 蛙飛び込む 水の音」という句では、無駄を省いて自然の一瞬をそのまま表現することが重要視されています。
また、井原西鶴の浮世草子には、人々の欲望や現実が描かれつつも、そこにはあるがままの人間の姿がリアルに描かれています。浮世草子は、日常的な生活や感情をそのまま表現することが多く、その意味で「あるがまま」の価値が見て取れます。
3. 近代文学における自己受容の探求
明治時代に入ると、西洋思想の影響を受けて、個人の意識や自己探求が文学のテーマとして取り上げられました。この時期における「あるがまま」の概念は、自己の受容や個人の心の葛藤に関するものへと発展します。
例えば、夏目漱石の小説では、自己の矛盾や現実との折り合いをどうつけるかという問題が中心的なテーマとなっています。漱石の作品に登場する人物は、自分をありのままに認識し、受け入れることができずに苦しむ姿が描かれることが多いです。その一方で、彼の作品は「ありのままの自分」を生きることの重要性を問いかけています。
また、芥川龍之介の作品では、精神的な葛藤や自己認識に関するテーマが多く、「あるがまま」の自己受容が重要なテーマとして描かれています。彼の短編小説「河童」や「地獄変」では、登場人物が自己の内面に向き合い、「あるがまま」を受け入れることが、生きる意味を見出す手段として描かれています。
4. 現代文学における「あるがまま」
現代文学においても、「あるがまま」の価値は重要なテーマです。特に、戦後の日本文学においては、戦争や社会的な混乱を経て、自己や他者のありのままを受け入れる姿勢が問われることが多くなりました。
村上春樹の作品では、現実と夢、そして自分と他者の境界が曖昧になり、「あるがまま」の存在の意味が深く探求されています。例えば、『ノルウェイの森』では、登場人物が自分自身や他者との関係をありのままで受け入れようとする姿が描かれています。
また、吉本ばななの作品でも、「あるがまま」の自分を受け入れることがテーマとなっています。彼女の作品では、人間の不完全さや弱さをそのまま受け入れることで成長が描かれ、個々の精神的な成長や癒しが重要なテーマとなっています。
あるがままに生きる意味を禅の思想とマインドフルネスで考察
「あるがままに生きる」という意味は、禅の思想やマインドフルネスにおいて深く根差した重要なテーマです。どちらも、物事をありのままに受け入れ、執着を手放し、現在の瞬間に集中することを重視します。ここでは、禅とマインドフルネスのそれぞれのアプローチに基づき、どのように「あるがままに生きる」ことが意味を持つのかを考察してみましょう。
1. 禅の思想における「あるがままに生きる」
禅は、「今、ここ」に集中し、思考や感情をありのままに受け入れることを重要視する仏教の修行方法です。禅における「あるがままに生きる」は、以下のような観点で考えられます。
無為自然(むいしぜん)
禅の教えにおいて、「無為自然」は中心的な概念です。これは、無理に何かをしようとするのではなく、自然の流れに身を任せ、ありのままの状態で存在することを意味します。禅僧は、日々の生活の中で、無駄な思考や行動を排除し、物事をそのままに見ることを大切にします。この姿勢は、心の中での抵抗や執着を取り除くことによって、真実の自己と調和した生き方を目指すものです。
禅の思想における「あるがまま」とは、物事や自分自身に対して、過剰な解釈や期待をせず、ありのままの姿を受け入れることです。例えば、坐禅の修行では、ただ坐ることによって、思考を手放し、現れる感情や思いをそのままに感じることが求められます。このように、禅では「あるがまま」は、物事の本質をありのままに体験し、執着を手放すことによって精神的な解放を得る道とされています。
一切皆空(いっさいかいくう)
「一切皆空」は、すべての物事が無常であり、執着や固定観念から解放された状態に至ることを意味します。禅の教えでは、すべてのものは空であり、それに執着することから解放されることが求められます。したがって、「あるがままに生きる」とは、物事の無常を受け入れ、今ここにあるものをそのままに受け入れ、過去や未来にとらわれないことです。過去の出来事に執着することなく、未来の不安に悩まされることなく、現実に存在しているものをそのまま感じることが、禅の「あるがまま」の生き方です。
2. マインドフルネスにおける「あるがままに生きる」
マインドフルネス(Mindfulness)は、現在の瞬間に意識的に注意を向け、過去や未来にとらわれずに自分の経験を受け入れる心の状態を指します。マインドフルネスは禅と密接に関連しており、心の静けさと自己受容を育むための実践法です。
現在に集中する
マインドフルネスの核心は、「今、ここ」に意識を集中し、過去や未来の思考から解放されることです。「あるがままに生きる」とは、未来の不安や過去の後悔にとらわれず、現在の瞬間をそのままに感じることです。マインドフルネスでは、呼吸や身体の感覚、感情に注意を向け、そのままに感じることで、心の中の雑念を取り除くことができます。これにより、心の平穏が生まれ、現実の瞬間に対する受容が深まります。
評価や判断を手放す
マインドフルネスは、物事を良い悪い、正しい間違いで判断することなく、ただそのままを受け入れることを勧めます。日常生活においても、自分や他人に対する評価を手放し、現れる感情や思考をそのままに認識することが重要です。マインドフルネスの実践においては、感情や思考を「ただの思考」「ただの感情」として受け入れ、それに対して反応するのではなく、観察することが求められます。これにより、内面の混乱を減らし、より平穏で安定した心の状態を保つことができます。
自己受容
マインドフルネスにおける「あるがままに生きる」とは、自己をありのままに受け入れることでもあります。過去の失敗や欠点にとらわれず、現在の自分をそのまま受け入れることが大切です。自己批判や自己否定を手放し、今の自分を認めることで、心の安定が得られます。自分自身をありのままに受け入れることが、他者や世界に対しても同じように寛容でいられる力を育むのです。
3. 禅とマインドフルネスの共通点と相違点
共通点:
・どちらも現在の瞬間に意識を集中し、過去や未来にとらわれずに「あるがまま」に生きることを重視します。
・思考や感情を評価や判断なしにそのまま観察し、受け入れることが重要です。
・執着を手放し、自己受容と精神的な解放を目指します。
相違点:
・禅は修行を通じて「無為自然」や「空」の境地に達することを目指し、精神的な覚醒や悟りを目指す側面があります。
・マインドフルネスは、日常生活におけるストレス管理や心の安定を重視し、実生活の中で実践可能な心の状態を育むことに焦点を当てています。
森田療法における「あるがまま」は、禅やマインドフルネスと共通する深い哲学的な背景を持ちながらも、具体的に実践的な心理療法としての役割を果たしています。森田療法は、精神的な問題や不安障害、神経症的な症状に対するアプローチとして、無理に症状を取り除こうとするのではなく、あるがままに受け入れ、自然に対処していくことを重要視します。このアプローチには、禅やマインドフルネスにおける「現在の自分を受け入れる」や「物事をありのままに見る」といった共通点があります。
以下、森田療法におけるあるがままについて、久保田幹子先生に詳しく解説していただきます。
森田療法における「あるがまま」とは
法政大学大学院人間社会研究科臨床心理学専攻 教授
久保田 幹子(くぼた みきこ)
心理学ワールド 87号 「あるがまま」の心理学 森田療法における「あるがまま」とは | 日本心理学会
森田療法における「あるがまま」とは
Profile─久保田 幹子
東京慈恵会医科大学森田療法センター臨床心理長を兼務。上智大学大学院文学研究科臨床心理学専攻博士後期課程満期退学。1998〜2000年,ミシガン大学精神神経科にて認知行動療法と入院・外来治療の研修,および精神分析的精神療法の研修を受ける。2006年より現職。専門は森田療法,比較心理療法,臨床心理学。著書は『女性はなぜ生きづらいのか:森田療法で悩みや不安を解決する』(共著,白揚社),『森田療法で読む強迫性障害:その理解と治し方』(共著,白揚社)など。
森田療法は1919年に森田正馬によって創始された神経症に対する心理療法である。今年で100年の歴史をもつ日本独自の治療法であるにもかかわらず近年までその詳細はあまり知られていなかったが,入院治療から外来森田療法が昨今主流になり,多くの心理臨床家が学び,実践している。「あるがまま」は森田療法の鍵概念である。平易な言葉である一方,その意味を理解することは難しい。そこで本稿では,森田療法の理解と介入を概説しつつ,森田療法における「あるがまま」について解説する。
森田療法における神経症の理解と治療目標
森田療法における「あるがまま」を語るには,まず森田療法における神経症の理解の仕方を説明する必要があるだろう。
森田療法の特徴は,神経症者が問題としている「不安」を病理ではなく,自然な感情と理解する点であろう。多くの心理療法(精神療法),とりわけ西洋の学派では,不安を病理として理解し,その原因を探求し,不安や症状の消去や解決を目指していく。しかし森田療法では,『根本的な恐怖は,死の恐怖であって,それは表から見れば,生きたいという欲求であります』と森田が述べているように,不安は「より良く生きたい」という欲求(生の欲望)の裏返しと捉えていく。つまり「こうありたい」という願望がなければ,それが損なわれる不安も生じないとし,あくまでも人間にとって避けられない自然な感情と理解するのである。ここに森田の人間観と森田療法の独自性がある。
それは,『「欲望はこれをあきらめることはできぬ」〜「死は恐れざるを得ず」との二つの公式が,私の自覚から得た動かすべからざる事実であります』といった森田の言葉からもわかるように,まさに自身の体験から実感している人間理解と言ってもよいだろう。
ではどうして自然な感情である不安が神経症を生み出すのだろうか。それを森田は「とらわれの機制(悪循環)」として説明した。つまり,不安そのものが問題なのではなく,不安に対する態度が神経症に繋がると考えたのである。
「とらわれの機制」は二つの要素から成るが,その一つは,注意と感覚が相互に影響することによって生じる悪循環(精神交互作用)である。例えば,人前で顔がこわばる自分に不安・違和感を抱き,表情に注意が集中すると,より感覚が敏感になり,さらに不安がつのって一層顔がこわばるというように,注意と感覚が相互賦活的に作用して症状が強まる機制である。もう一つは思想の矛盾と呼ばれるもので,悪循環を生じさせる構えである。とらわれやすい人々は,自然に生じる感情を「かくあらねばならない」と考え,知的に解決しようとする。これは自然や心身を支配しようとする万能感,もしくはコントロール欲求ということもできるが,不快な感情を「あってはならないもの」として観念的にやりくりしようとするために,より一層思うようにならない自己(理想の自己と現実の自己とのギャップ)に葛藤が生じるのである。これは不可能を可能にしようとする試みであり,先の例であれば,「人前ではきちんとしていなければならない」と考えるために,緊張してしまう自分を「ふがいない」と感じ,緊張しないようにと身構える結果,かえってそれにとらわれてしまうといったものである。
森田は,不安の対象はさまざまであっても,「とらわれ」が生じる背後には共通の性格傾向があることを見出し,それを神経質性格と名づけた。神経質性格とは内向的,自己内省的,心配性,敏感といった弱力的な側面と同時に,完全主義,理想主義,頑固,負けず嫌いといった強力的な側面を持ち,内的葛藤を生じやすいことが特徴である。
先に述べたように,森田療法では不安と欲求は表裏一体とみなすが,神経質性格を持つ者は「かくあらねばならない」と自らに完全を求めるがゆえに(思想の矛盾),不安や違和感を抱くと,それを特別視した上で排除しようとして,より一層とらわれる(悪循環)結果,神経症に発展すると理解するのである。
したがって治療目標は,この「とらわれ(悪循環)」からの脱出と,本来の欲求(生の欲望)を自分らしく発揮できるよう援助することに据えられる(図1)。そこでは,不安や症状の原因を探ること,あるいはそれを直接解決することに焦点づけをしない。あくまでも不安も欲求(生の欲望)も自然なものとして「あるがまま」に受けとめる姿勢(受容)を培うと共に,本来の欲求(生の欲望)にも「あるがまま」にしたがって目前の生活に関わり自己を成長させるよう促していく。こうしてとらわれからの脱却を図ると共に,ありのままの自己を受けとめ,生の欲望に則って自分らしい生き方が実現できるよう(自己実現)援助していくのである。
図1 病理の理解と治療目標(久保田,2009をもとに著者改変)
「あるがまま」の姿勢とは
では,森田療法における「あるがまま」とはどのような姿勢を指すのであろうか。森田の言葉も紹介しつつ,具体的に振り返ってみたい。
①不安に対する「あるがまま」
「あるがまま」の一つは,不安に対する態度である。すなわち,不安も自然な感情の一つとして,「そのまま」つき合う姿勢を指す。森田は『「柳は緑,花は紅」である。〜憂鬱や絶望を面白くし,雨を晴天にし,柳を紅にしようとするのが不可能の努力であって,世の中にこれ以上の苦痛なことはない』『夏は暑い。嫌なことは気になる。不安は苦しい。雪は白い。夜は暗い。なんともしかたがない。それが事実であるから,どうとも別に考え方を工夫する余地はない』と述べている。つまり,不安も境遇も自分の思い通りにはならないものであって,自然なありのままの事実として,「そのまま」受けとめることを促しているのである。そこには「納得」も「受け入れる」姿勢も不要である。事実は変えられないものとして,仕方がないと受けとめるということである。
②欲求(生の欲望)に対する「あるがまま」
もう一つの「あるがまま」は本来の欲求に対する態度である。すなわち,「こうありたい」という自らの欲求も「そのまま」受けとめ,それに従って行動に移す姿勢である。その際,森田は『時間がたてば腹がへり,ご馳走を見れば食べたくなる。これが「感じ」である』と述べているように,おのずと湧き起こる欲求を重視している。これは,観念的に理屈をつけたり,「価値ある行動」「万全な行動」を求めてしまう神経症者に対し,自らの欲求のままに動くだけで十分,と伝えようとするものである。
このように,森田が述べる「あるがまま」とは,不安のやりくりは不可能な努力とし,事実は事実としてそのまま受けとめる姿勢と同時に,生の欲望に従って日常生活に関わる姿勢を促すといった二つのメッセージを含んでいる。
「あるがまま」の姿勢をどのように培うか
では,神経症者はどのように「あるがまま」の姿勢を身につけ,「とらわれ」から脱していくのであろうか。
実際,不安に圧倒され,それを必死に取り除こうとしている患者にとって,不安と付き合いつつ行動することは決して容易なことではない。それを後押しするものとして,以下がポイントと言えるだろう。
①不毛な試みとそこに潜む感情を共有
不安を排除する試みは本当の解決に繋がっていない事実(悪循環)を繰り返し拾い上げ,不毛な努力であることを共有していく。それ以上に,求めていた生活も結果的に失っている事実を伝えながら,患者が感じている悔しさやジレンマなどの感情に焦点を当て,欲求があるからこそのジレンマと理解し,それを原動力に一歩踏み出してみるよう励ましていく。
②感情の法則(図2)
森田が「感情の法則」として明確化した感情の特性を伝えていく。すなわち,不安もどのような感情もそのまま放任すれば,時を経るにしたがって自然に消失することを伝え,時間の経過を待つよう促していく。
図2 感情の法則
③「せめて」「とりあえず」の姿勢
しかし,「不安がいつおさまるのか……」とにらめっこをしていては常に注意は不安に集中してしまう。森田療法では,行動を通して注意の転換を図っていく(図2下)。ただし,その行動は症状克服のための試みである必要はなく,生活上のどんな些細なものでも構わない。不安を感じながらでも,何かしらに手が出せるよう,「とりあえず」「せめて」とわかりやすい言葉で後押しをしていくことが重要である。
④比喩の活用
これまでの例でもわかるように,森田は治療においてかなり比喩を活用している。それは,観念的な神経症者に対する説得や説明が逆効果であることを熟知しているからであり,身体を通した実感を掴ませようとする臨床的工夫と言える。実際,著者も臨床場面において比喩やたとえ話はかなり活用している。例えば,「春が来ない冬はない」「台風は嫌だが,いつかは通り過ぎる」「突然ゲリラ豪雨にあったらどうするか? 雨をやますことはできないが,雨宿りやコンビニで傘を買うなど,何か対処するのでは? 不安もそれと同じ」などである。これは不安を特別視し,まず排除しようとする患者に対し,日常体験に照らしながらその付き合い方を伝えるための介入である。
これらの関わりを通して,「不安なまま(不安はそこにあるまま)」「せめて,何ができるか」を問い,患者自らの試行錯誤と患者自身の体験を促していく。観念的構えを打破するには,「百聞は一見にしかず」で,患者自身の体験の積み重ねが必須なのである。
森田療法における「あるがまま」とは
ここで事例を紹介する。パニック症の女性のAさんは,息苦しくなるとすぐに病院に駆け込んだり,実家に逃げ込む生活を送っていたが,森田療法の介入を続ける中で少しずつ,不安をすぐに回避せず,できることを試行錯誤するようになっていった。何とかなる経験を得る中で,Aさんは次のように語った。「美容院でパーマをかけている最中,息苦しくなってきた。まずい!と思ったが,不安はまた来るものなんだ,しょうがないと思った時に,最近髪の毛が痛んでいるのが気になっていたのでそのことを聞いてみようと思って,美容師さんに手入れの方法を質問してみた。それを聞いているうちに息苦しさは軽くなっていた」。
また不潔恐怖症に悩んでいた女性Bさんは,洗浄強迫行為のために外出もままならない状態だった。しかし,治療を通して際限ない手洗いの疲労と不毛さを自覚し,少しずつ生活の幅を広げていった。好きなライブもこれまで症状のために諦めてきたBさんだったが,どうしても行きたいと思って行動に移したところ,本当に幸せな気持ちで帰ってくることができた。
この二例からもわかるように,森田療法における「あるがまま」とは,不安も含めた感情は思い通りにならないものとして付き合い,同時にそこでできることを探る姿勢である。その際最も重要となるのは,観念的理解ではなく,様々な体験を通した実感・理解と言える。森田が『「あるがまま」になろうとしては,それは「求めんとすれば得られず」で,すでに「あるがまま」ではない。なぜなら「あるがまま」になろうとするのは,実はこれによって,自分の苦痛を回避しようとする野心があるのであって,苦痛は当然苦痛であるということの「あるがまま」とは,まったく反対であるからである』(8)と述べている。自らを観念的に操作しようとすれば,単に新たな「とらわれ」を生むだけだからである。
患者は,セラピストに支えられ試行錯誤を繰り返す中で,「できないこと(感情のコントロール,過去・未来・他人など)」と「できること(感情との付き合い方,行動の仕方)」の両方がある事実を知り,全てを思い通りにすることは不可能な現実を知ることになる。それは「快・不快,好き・嫌い,得意・不得意,完全・不完全」など,感情にも事象にも全て両面があるという事実,それが自然であることを受けとめるプロセスである。こうした事実を体験を通して知ることが,森田療法における「あるがまま」と言えるだろう。
最後に,昨今共通点が指摘されている第三世代の認知行動療法との違いについて多少触れておく。マインドフルネス認知療法では,マインドフルネス瞑想という特有の方法で,意図的に「価値判断をはさまず」注意を払うことによって感情の気づきを促していく。またACTは,こうしたマインドフルネスやアクセプタンスによる感情の気づきや受容と,行動活性化を段階的に進めていくことが特徴と言える。一方森田療法では,自然にわき起こる感情や,行動を介して生じる感情体験に焦点を当て,その自覚を促していく。つまり,マインドフルネスのように感情をあえて観察することを主目的としない。森田療法では,不安排除の姿勢を一時的に封じ込めることと,生の欲望を原動力にした外界への関与を同時一体的に促すことによって,症状からの脱焦点化を図り,とらわれを打破していく。それは,症状排除のみに使われていたエネルギーの方向性を変えるといった転換を図る関わりであり,同時に神経質を生かすことに通じる。患者は,健康な欲求に着目する治療者に支えられつつ,様々な感情のみならず,ありのままの自己の受容を深めていくのである。
おわりに
森田療法における「あるがまま」について述べてきた。「仕方がない」と現実を受けとめることは,自らの限界を知ることでもあるが,それは単なる諦めではなく,本来の欲求を生かすためにどこに力を注ぐかといった自己実現の方向性を見出すことにも繋がっていく。森田療法が「とらわれ」の打破のみならず,生き方を支援する治療法と言われるゆえんはそこにあるのである。
文献
- 久保田幹子(2009)対人恐怖の森田療法.『こころの科学』147,72-78. 日本評論社
- 久保田幹子(2012)森田療法における受容:体験を通した受容のプロセスについて. 『日本森田療法学会誌』23, 41-45.
- 森田正馬(1926)神経衰弱及強迫観念の根治法. 『森田正馬全集 2』71-278. 白揚社
- 森田正馬(1928)神経質ノ本態及療法. 『森田正馬全集 2』281-442. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 4』41. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 5』113. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 5』188. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 5』406. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 5』710. 白揚社
- 森田正馬(1974)『森田正馬全集 7』62. 白揚社